はじめに【複雑なる望郷の念】
ふるさとは遠きにありて思ふもの
そして悲しくうたふもの
よしや
うらぶれて異土の乞食となるとても
帰るところにあるまじや
(『小景異情(その二)』)
これは室生犀星の有名な詩の一節ですが、ふるさとを離れた人の多くが、一度や二度は、この詩のような心理状態になるような気がします。わたし自身もやむを得ぬ事情で、ふるさとを離れて暮らすようになりました。
今でも時々ふるさとのことを思い出します。その記憶はどこか甘酸っぱくもあり、ほろ苦くもあり、まるで初恋のときの記憶のようです。
魯迅『故郷』あらすじと解説【希望とは地上の道のようなもの!】
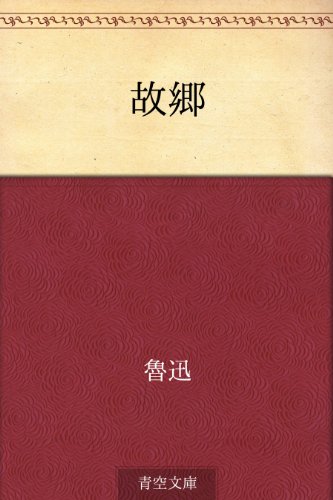
魯迅(ろじん)とは?
魯迅(本名は周樹人)は中国の小説家、翻訳家、思想家です。(1881‐1936)
魯迅は1881年8月3日、浙江省紹興の裕福な階級の家に生まれます。しかし幼時に没落し、苦労も体験しながら、18歳のとき南京の江南水師学堂(海軍養成学校)に入学します。
その3年後の明治35(1902)年、官費留学生として日本に派遣され、仙台医学専門学校に入学します。しかし中退し、文学の道を志します。明治42(1909)年に帰国し、文学の研究・翻訳をしながら『狂人日記』『阿Q正伝』を著します。
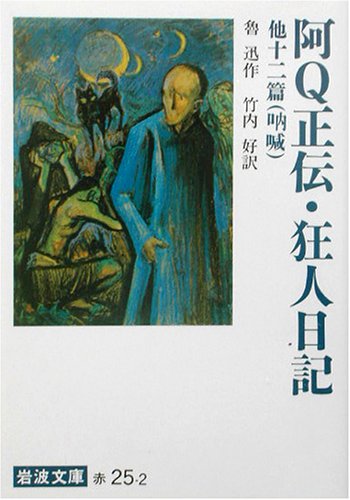
その後、『故郷』『祝福』『孤独者』などの小説と散文詩や、多くのエッセーを書き中国文学の中心的存在となります。1930年、左翼作家連盟発足後はその実質的な指導者となります。1936年10月19日、持病の喘息の発作で急逝します。(没年齢55歳)
中国で最も早く西洋の技法を用いて小説を書いた作家であり、その作品は、中国だけでなく、東アジアでも広く愛読されていて、日本でも中学校用の国語教科書に作品が収録されています。

魯迅
小説『故郷(こきょう)』について
『故郷』は、魯迅の代表作ともいえる短編小説のひとつで、1921年5月号の『新青年』に発表され、『吶喊』(1923年)に所収されます。
日本においては昭和2(1927)年に、武者小路実篤の主宰する月刊誌『大調和』10月号に掲載されます。その後多くの人間によって翻訳され、日中国交回復の昭和42(1972)年以後は、中学三年生の国語教科書に収録されるようになります。
ちなみに、作品に描かれた主人公の生家の没落、故郷からの退去は、魯迅本人の経験がもととなっています。
『故郷』【物語の時代背景】
.jpg)
魯迅が生まれた当時の中国は、清王朝(または大清帝国1616 – 1912)末期で、ちょうど欧米列強がアジアの植民地化政策を推し進めていた頃と重なります。いわゆる激動期でした。
魯迅は、清と日本との間で行われた日清戦争(1894-1895)後の1902年、日本に留学します。七年余りを日本で過ごした魯迅は、1909年に帰国します。この二年後、辛亥革命(清で発生した共和革命1911年)が起こり、清王朝は滅亡しました。
1912年に中華民国政府が成立すると、魯迅は、南京に行き教育部の事務官の職位に就きます。その後、臨時政府の移転にともない北京に移り住みました。この頃から魯迅の執筆活動は精力的になっていきます。

魯迅は1920年から1926年まで、北京大学や北京師範大学の講師を務めます。『故郷』が発表されたのは1921年です。また1921年という年は、上海で中国共産党が成立した年でもあります。
つまり、国民革命(1920年代に高まった中国の革命運動)幕開けの混乱期に『故郷』は世に出されたのです。
『故郷』あらすじ(ネタバレ注意!)

物語は1920年前後の中国を舞台としています。
主人公の「私」は、二十年ぶりに帰ってきた故郷を目にし、思わず寂寥感が胸にこみあげてきます。記憶の中では美しかった故郷も、今ではすっかりと色褪せて、少しの活気もなくなっていたからでした。
しかし「私」は思い直します。―――これは自分自身の心境の変化からくるものだと。
帰省の理由は、慣れ親しんだ生家を引き払うためでした。「私」の生家はかつてこの土地の地主でしたが没落してしまい、家屋は既に公売され、年内には出て行かなければならなかったのです。
二十年ぶりに訪れた我が家もまた廃れ、辺りはひっそりとしていました。生家に着くと、母と八歳になる甥の宏兒が飛び出してきて「私」を迎えてくれます。「私」は寂しい気持ちを押し殺しながら転居のことについて話します。

転居先での家具は準備をしましたが、まだ足りず、生家にある物を売ってお金にしなければならなかったのです。そんな「私」の寂寥感が、母の口から出たふいの一言で一変します。
「あの閏土がね、お前に逢いたいと言っているんだよ。」
そのとき「私」の頭の中に、一片の素晴らしい光景が浮かび上がってきます。それは―――三十年も昔の閏土との記憶でした。記憶といっても「私」が実際に見た光景ではなく、閏土が語って聞かせてくれた光景のことです。
その頃はまだ父親も存命で「私」は、いわゆる “ お坊ちゃま ” でした。この年、「私」の家では三十何年目に一度廻ってくる正月の大祭の番で、小作人の子・閏土が手伝いにやって来ます。年齢も同じくらいの閏土と「私」はすっかり仲良しになります。
.jpg)
そのとき閏土が語って聞かせてくれた話は、「私」にとってどれも興味深く、とても神秘的なものでした。鳥を捕まえる話、海辺の貝殻や跳ね魚の話、西瓜畑で土竜のような動物を退治する話。「私」はたちまち閏士の虜になります。
それもその筈です。―――当時の「私」は、塀に囲まれた屋敷の上の四角な空ばかりを眺めていたのですから。閏土は「家に遊びにおいで」と「私」を誘います。しかしその閏土も郷里に帰るときがやってきます。その時は、お互いに離れたくないと大泣きに泣いたものでした。
そんな光り輝く一片の素晴らしい記憶が「私」の中に蘇ってきて、そこに美しい故郷を見出したような気がしたのです。ところが、かつては「豆腐屋小町」と呼ばれたほどの美人だった楊おばさんの出現によって現実へと引き戻されるのでした。
楊おばさんは三十年の歳月の中で見事に変貌を遂げていました。頬骨が出るくらい痩せ細っています。しかも野放図な性格に生まれ変わり、「私」の生家の家財道具を盗もうとして目を光らせているのでした。
※ 野放図 しまりがなく何をするか分からないこと。際限のないこと。

それから三、四日後、閏士が息子を連れてやって来ます。閏士もまた、驚くほどの変貌を遂げていました。けれども昔の面影は残しています。「私」は万感の思いでいっぱいになり、言葉が思ったように出てきません。
そのとき閏士は「私」に向けて―――「旦那様。」と呼びました。
「私」はその言葉に圧倒され、もはや返す言葉もありませんでした。変わったのは姿だけではなく、二人の関係性もだったのです。そんな二人の隔たりとは関係なく、閏士の息子の水生は甥の宏児と一緒に遊び始めます。
閏士が帰ったあと、母と「私」は彼の境遇を思って溜息をつきます。子だくさん、凶作、重税、匪賊や兵隊、役人や地主、みんなが彼を虐めて、デクノボーのような人間にしてしまったのです。母は「私」に「要らない物は何でも彼にやるがいい。」と、言いました。
※匪賊(ひぞく) 集団で略奪などをはたらく盗賊。

「私」が故郷の土を踏んでから九日目、とうとう出発の日がやってきます。閏士も見送りに来ました。―――船上で甥の宏児が、水生から「家に遊びにおいで」と誘われたことを「私」に言って聞かせます。
眠くなる頃、母は閏士の話を持ちだします。例の楊おばさんが昨日、灰の中から椀や皿を十幾枚も彫り出して「きっと閏土が埋めておいたに違いない」と手柄のように話し、それを掴んで駆け出して行ったことを。
次第に故郷の山水も遠ざかっていきます。けれども「私」は、名残惜しい気はしませんでした。ただ、一時鮮明に浮かんできた閏土との美しい記憶が、薄らいでいくことだけが、たまらなく悲しかったのです。

「私」は願います。宏児と水生のような若い世代は、互いに隔絶することのないようにと。それはひとつの希望でした。希望とは地上の道のようなものです。もともと地上に道はなく、歩く人が多くなると、それが道になるのですから。
※隔絶(かくぜつ) へだたり、掛け離れること。
青空文庫 『故郷』 魯迅 (井上紅梅訳)
https://www.aozora.gr.jp/cards/001124/files/42939_15330.html
あとがき【『故郷』の解説と感想を交えて】
小説『故郷』は、「私」のふるさとへの帰郷を通して、移り変わる時代の混乱、または社会や国家のあり方を問題にした作品と言えるでしょう。
物語の時代背景でも触れましたが、『故郷』が描かれた当時、中国は辛亥革命が成功を収め、民主共和国を出現させました。しかし列強の侵略を食い止めることもできず、革命によって救われるどころか、人民の困窮は清朝末期よりも酷い有り様になっていたのです。
物語の中で「私」は、変貌した楊おばさんや閏士に幻滅します。しかしそれは、かつては富裕階級に属していて、当たり前のように学問を受けていた自分への幻滅でもあったのです。
魯迅は『故郷』で、世の中を憂いています。その一方で読者に “ 希望 ” を見せています。つまりは若い世代への期待です。しかしそれは結局、他者への期待であり、自分自身が行動しなければという思いに至るのです。
実際に魯迅は、志半ばではありましたが「ペンは剣よりも強し」の如く、筆を持って社会を変えようと動きました。そんな魯迅が現代の祖国を見て何を思うかは知る由もありません。しかし、その作品は現代にも読み継がれています。
ともかくとして『故郷』を読むたびにしみじみ思うのですが、幸せな時代に生まれたものだと。わたし自身、食うや食わずの貧しい少年時代を過ごしました。が、戦争や騒乱には遭遇しませんでした。
どうか次の世代にも平和な世の中を届けたいものですね。




コメント