はじめに【共同体(コミュニティ)について】
わたしたちは、何かしらの共同体に属し、日々の生活を送っています。しかし、それは強制されたものではなく、人間の持つ「集団欲」といった本能によるところが大きいでしょう。
現代社会ではインターネット上での集まりのように、共同体の形も個人の欲求に伴い、多様化していっています。けれども、そのいずれの集団にも属せない、いや、属すことのできない人間が多くいることも現実です。
それは一体なぜなのでしょうか。知らず知らずのうちに、わたしたちが人を選別しているからに他なりません。人に好き嫌いがあるのは当然です。だからといって、共同体から拒絶された人間はどこに行けば良いのでしょう。家に閉じこもるしかありません。
住む家があるならまだしも、家のない人はどこに行けば良いのでしょうか。
―――街をさまよい歩くしかないでしょう。
人々のこころとこころを繋いで結ぶ!【『結い』を考える】
こころの支えと安心は地域から!【結い・もやい・講】
安部公房『赤い繭』あらすじと解説【社会から受ける疎外感!】
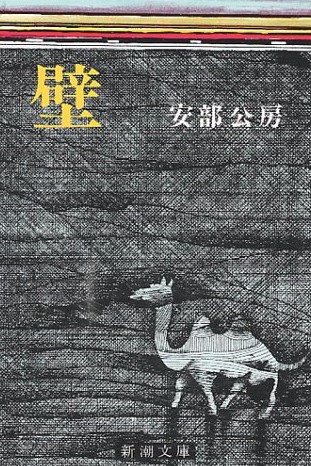
安部公房(あべこうぼう)とは?
安部公房(本名・公房きみふさ)は、昭和から平成初期にかけて活躍した日本の小説家・劇作家です。(1924~1993)
安部公房は、大正13(1924)年3月7日、東京府北豊島郡滝野川町(現・東京都北区西ケ原)に生まれます。生後8ヶ月で家族と共に満州に渡り、幼少期から少年期にかけて奉天で過ごします。
昭和15(1940)年、日本に帰国し、旧制成城高等学校 (現・成城大学) 理科乙類に入学します。昭和18(1943)年、東京帝国大学医学部医学科に入学します。奉天帰省時、そこで敗戦を迎えます。

帰国後の昭和23(1948)年に東京帝国大学医学部を卒業しますが、医師の道は目指さず作家を志します。『終りし道の標べに』で作家としてデビューします。昭和26(1951)年、『壁 - S・カルマ氏の犯罪』で第25回芥川賞を受賞し、以後数々の人気作を発表していきます。
世界的に評価が高く、昭和43(1968)年にはフランス最優秀外国文学賞を受賞しています。特に東欧において高く評価され、西欧を中心に評価を得ていた三島由紀夫と対極的とみなされていました。
平成4(1992)年、急性心不全により死去します。ノーベル文学賞に最も近かった作家の急逝でした。(没年齢・68歳)他に代表作として『けものたちは故郷をめざす』『石の眼』『砂の女』『箱男』『他人の顔』『榎本武揚』等があります。

安部公房『鞄』あらすじと解説【選ぶ道がなければ迷うこともない!】
安部公房『棒』あらすじと解説【弱い人間は強い人間の道具?】
安部公房『詩人の生涯』あらすじと解説【貧しさの為に貧しく!】
安部公房『洪水』あらすじと解説【堕落した人類の結末!!】
安部公房『事業』あらすじと解説【道徳をよそおうことが道徳!】
小説『赤い繭』(あかいまゆ)【短編集『壁』について】
安部公房の『赤い繭』は、昭和25(1950)年12月発行の雑誌『人間』に、「三つの寓話」というタイトルで『洪水』『魔法のチョーク』とともに発表された短編小説です。
翌年の昭和26(1951)年5月、『S・カルマ氏の犯罪』『バベルの塔の狸』とともに短編集『壁』に所収されます。ちなみに『赤い繭』は、昭和40年代から高等学校の教科書教材に採用されていて、作品として多くの方に親しまれています。
『赤い繭』あらすじ(ネタバレ注意!)

日が暮れかかっても、主人公の「おれ」には帰る家がありません。「おれ」は住宅街をさまよい歩きながら(家がないのは何故だろう?)と疑問を覚えます。道端に縄が落ちているのを見ると首をつりたくなります。
けれども、家がない理由が見つかるまで、そんなことはできません。夜は毎日やってきます。夜がくれば休むために家が必要です。「おれ」はふと思いつきます。(家がないのではなく、単に忘れてしまっただけなのかもしれない)と。
そこで「おれ」は、偶然通りかかった家のドアを叩き、窓から顔を覗かせた女性に「ここは私の家ではなかったでしょうか?」と、訊ねます。当然のように女性は「私の家ですわ。」と答え、窓を閉めてしまいました。

(何故すべてが誰かのものであるのか?)そう考えた「おれ」は、公園のベンチを家とすることにします。けれども棍棒を持った彼に「ここはみんなのもので、誰のものでもない。」と言われ、追い立てられてしまいます。
「おれ」は、(さまよえるユダヤ人とは、おれのことであったのか?)と、思い至ります。けれども依然として家がない理由が吞み込めず、首もつれません。すると、「おれ」の足にいつの間にか絹糸がまとわりついています。
つまんで引っ張ると、ずるずるとのびていきます。好奇心にかられ、たぐりつづけていくと、なんと「おれ」の足がどんどんほぐれていくのです。そのうち絹糸はひとりでにほぐれ、糸はやがて「おれ」の全身を袋のように包みこんでいきます。

そして、ついに「おれ」は消滅し、後には大きな空っぽの繭だけが残ります。けれども、家が出来ても、今度は帰ってゆく「おれ」がいません。繭の中は夕焼け色に赤く光っています。
彼は繭になった「おれ」を、踏切とレールの間で見つけます。彼は繭をポケットに入れ、その後、繭は彼の息子の玩具箱に移されたのでした。
『赤い繭』が書かれた社会背景【プレスコードとレッドパージ】
敗戦直後の昭和20(1945)年9月、GHQ(連合国最高司令官総司令部)は、プレスコード(Press Code:新聞・出版活動を規制するために発した規則)を発し、厳しい言論統制を行います。この規則は昭和27年、講和条約が発効されるまで続けられました。
昭和25(1950)年、朝鮮戦争(1950~1953)が勃発します。この前後の時期、GHQは共産主義の思想・運動・政党に関係している者を公職や企業から追放するよう指示します。この一連の出来事をレッドパージ(Red purge:赤狩り)といい、約1万3千人が強制的に職場を解雇されました。

このような状況下で昭和25(1950)年、安部公房は『赤い繭』を執筆します。
『赤い繭』【解説と個人的な解釈】
敗戦時、奉天にいた安部公房は、家を追われ、奉天市内を転々とし、命からがら引き揚げ船に乗り込み、帰国を果たします。安部は、短編集『夢の逃亡』のあとがきで「当時、私には長い間、住む家がなく、また金がなく、したがって飢え疲れていた。」と語っています。
5年後の昭和25 (1950)年、安部は日本共産党に入党します。社会背景にも書いたように、同時期レッドパージが行われ、解雇された人の中には家(寮)を失い、路上をさまよい歩くことしかできなかった者がいたとされています。
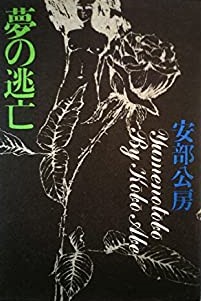
これらの出来事は、ちょうど『赤い繭』を執筆していた時期と重なります。もしかしたら安部は、同じ共産主義の失業者への同情とともに、中国で流浪をしていた自分を重ねて合わせていたのかもしれません。また、安部公房は古林尚氏との対談の中で『赤い繭』について以下のように語っています。
イマジネーションを展開していって、自然にそこに落ち着いたというのは、要するに帰属にたいする反感だろうなあ、結局は。もっとも、ああいうイメージをつくってしまったのには、心のどこかに帰属しなければ異端になるぞという不安もあったのかもしれない。反発と不安の両方なんだろうな。なにしろ、ぼくにはいまでも根強く、共同体そのものから受ける疎外感が存在している。
(『戦後派作家対談13 安部公房篇』図書新聞)
以上のことを踏まえ『赤い繭』という小説を考察してみると、作者が、明らかな政治的な意図のもとに創作したと考えるのが自然でしょう。そして厳しい言論弾圧の中では、それを表現する方法は、前衛的・革新的な手法しかなかったのです。
ここからは個人的な解釈になります。
物語の中で「おれ」は、自分の家を探して歩き続けていますが、その姿は社会から拒絶された人間を連想させます。「おれ」は、家のない理由(社会から拒絶される理由)を考え続けます。そして、家を忘れているだけ(自分の思い過ごし)と考えます。
けれども現実は、家を訊ねても(社会との融和をはかろうとしても)拒絶され、棍棒を持った彼(国家権力)からも追い立てられます。そこで「おれ」は、自分を “ さまよえるユダヤ人 ” (国を持たない民)だと思い至ります。
行き場を失った「おれ」は繭へと変身し(社会との融和を諦め)、再び世に出る機会を待ちます。繭の中は夕焼け色(共産主義者としての心の色)に赤く光っています。けれども繭は、彼のポケットに入れられて(国家権力に屈して)しまいます。
後に繭は、子供の玩具箱へと移されますが、それは次世代への思想の継承、そして期待だったのかもしれません。
さまよえるユダヤ人
ヨーロッパ伝説。刑場にひかれて行くキリストを辱しめた一人のユダヤ人が、死ぬこともできず永遠に放浪するという筋。ゲーテ、ワーズワースなどの詩にとりあげられ、ウージェーヌ=シューに同名の小説がある。永遠のユダヤ人。
出典:精選版 日本国語大辞典
あとがき【『赤い繭』の感想を交えて】

昨今、「SDGs」というワードを良く耳にするようになってきました。それに伴い各マスメディアは「マイノリティ(社会的少数者)」に焦点を当てることが多くなっています。けれどもそれは、マスメディアによって選別された「マイノリティ」です。
商売上、仕方のないことかもしれませんが、マスメディアというものは、発信力が強く、運動の大きな「マイノリティ」を選別して、報道をします。しかしながら本当の社会的少数派は声も上げられないのが実情です。
いや、声を上げる余裕すらないと言ったほうが適切かもしれません。生きるか死ぬかの問題を抱えている人間にとって、社会的地位の向上等はどうでもいいことなのです。ともかくとして、『赤い繭』を読む度に思うのはそのような人間の “ 社会からの疎外感 ” についてです。
冒頭でも書いたように、わたしたちもまた、知らず知らずのうちに、自分に合う人間を選別しています。つまりわたし自身もマスメディアをとやかく言える立場ではないのです。ただ、今からでもできることはある筈です。
それは、ひとりひとりが常に「寛容さ」を心の隅に置き、人を選別しないように努めることです。それだけでも社会(共同体)からの疎外感を抱く人間を減らすことができるでしょう。




コメント