はじめに【太宰治が『水仙』に引用した『忠直卿行状記』】
以前、太宰治の短編小説『水仙』を載せました。物語の語り手は、菊池寛の『忠直卿行状記』のことを思い出し、(その殿様は、本当に剣術の素晴らしい名人だったのではあるまいか。)と考え、夜も眠られないほどの不安を覚えます。
そして語り手は、自分の知り合いの草田静子氏に起こった出来事を語り、静子もまた、(天才だったのかも知れぬ。)と思い、奇妙な疑念に駆られてしまいます。
そんな訳で今回は、『水仙』に引用された菊池寛の短編小説『忠直卿行状記』のあらすじや解説を載せたいと思います。
太宰治『水仙』あらすじと解説【21世紀にも天才は存在する!】
菊池寛『忠直卿行状記』あらすじと解説【封建制の犠牲者!】

菊池寛(きくちかん)とは?
明治から昭和初期にかけて活躍した小説家、劇作家です。菊池寛。(1888~1948)
菊池寛(本名・菊池寛)は明治21(1888)年12月26日、香川県高松市に生まれます。明治43(1910)年に名門、第一高等学校文科に入学します。
第一高等学校の同級に芥川龍之介、久米正雄、山本有三らがいましたが、諸事情により退学してしまいます。結局、紆余曲折の末に京都帝国大学文学部に入学し、在学中に一校時代の友人、芥川らの同人誌『新思潮』に参加します。

大正5(1916)年、京都大学を卒業後、「時事新報」の記者を勤めながら創作活動を始め、『忠直卿行状記』『恩讐の彼方に』『藤十郎の恋』等の短編小説を発表します。大正9(1920)年、新聞小説『真珠夫人』が評判となり、作家としての地位を確立していきます。
大正12(1923)年、『文藝春秋』を創刊し、出版社の経営をする他にも文芸家協会会長等を務めます。昭和10(1935)年、新人作家を顕彰する「芥川龍之介賞」「直木三十五賞」を設立します。
しかし、終戦後の昭和22(1947)年、菊池寛は、GHQから公職追放の指令が下されます。日本の「侵略戦争」に『文藝春秋』が指導的立場をとったというのが理由でした。その翌年の昭和23(1948)年3月6日、狭心症を起こして急死してしまいます。(没年齢・59歳)

菊池寛『恩讐の彼方に』あらすじと解説【罪と償いを考える!】
菊池寛『芥川の事ども』要約と解説【天才ゆえの苦悩!】
菊池寛『奉行と人相学』あらすじと解説【人は見かけで分かる?】
菊池寛『形』と『常山紀談』あらすじと解説【虚妄に裏切られる!】
菊池寛『藤十郎の恋』あらすじと解説【女遊びは芸の肥やし?】
菊池寛『恩を返す話』あらすじと解説【人間関係が生み出す苦悩!】
菊池寛『マスク』あらすじと感想【強者に対する弱者の反感!】
菊池寛『父帰る』あらすじと解説【家族愛――「情」と「涙」!】
菊池寛『極楽』あらすじと解説【極楽に飽きて地獄に憧れる!】
短編小説『忠直卿行状記』(ただなおきょうぎょうじょうき)について
菊池寛の短編小説『忠直卿行状記』は大正7(1918)年9月号の『中央公論』に発表されます。
『忠直卿行状記』あらすじ(ネタバレ注意!)

「大坂夏の陣」のとき、越前少将・松平忠直の家老たちが本陣に呼びつけられ、家康から叱り飛ばされました。越前勢が合戦を傍観していたと言うのです。国老の本多富正は、このことを主君の忠直卿にどう切り出してよいか当惑していました。
※傍観(ぼうかん) そばでながめること。当事者でないという立場・態度で見ること。
大将の越前少将・松平忠直は二十一歳になったばかりです。十三歳で当主となって以来、人から𠮟責されることなど知らずに育ってきました。家老たちは恐る恐る家康の言葉を告げます。
それを聞いた忠直卿は逆上して、「忠直に死ね!というお祖父様の謎じゃ。其方たちも死ね!我も死ぬ!」と叫び、小姓の持っていた佩刀を抜き放つと、二度三度打ち振ったのです。忠直卿は時々このような狂的な発作にとらわれるのでした。

元和元(1615)年5月7日、3万の越前兵は、軍令を待たずに攻めかかります。大将忠直卿は今日を必死の覚悟と見えて、馬を先へ先へと進めました。大将に続けと越前の軍兵はことごとく奮い立ちます。そして真田勢を一気に切り崩すと、左衛門尉真田幸村を討ち取ったのでした。
さらに越前勢は大坂城への一番乗りも果たします。この活躍に家康は、「天晴、日本樊噲とは御身のことじゃ。」と忠直卿を褒め立て、秘蔵の初花の茶入を与えました。この上ない面目を施した忠直卿は、その年の8月、越前の福井へと下りました。
樊噲(はんかい)
出典:精選版 日本国語大辞典
中国、漢の高祖劉邦の功臣。沛の人。紀元前206年、楚王項羽と劉邦とが鴻門に会した際、謀殺されそうになった劉邦を機転をもって脱出させた。のち、劉邦が漢王になると将軍になり功をなした。前189年没。
忠直卿は、国に就かれて以来、昼間は武術の大仕合を催し、夜は酒宴を開くのを常としていました。家康から日本樊噲と呼ばれたのが嬉しくて堪らなかったのです。この日も忠直卿は、槍術に優れた家臣を集めて紅白の大仕合を催します。そして自らも紅軍の大将として出場したのでした。

仕合は紅組の方が始終不利でした。ところが忠直卿が出場すると形勢があっという間に逆転します。白組の副将・大島左太夫は槍を取っては家中無双の名誉を持っていました。そんな左太夫でさえも忠直卿の槍に、胸の急所を一突きされてしまいます。
白組の大将は小野田右近と言いました。槍術の名人・権藤左門に弟子入りし、二十歳のときには師を上回るほどの腕を誇っていました。しかし忠直卿は猛然と突きかかって行きます。激しい戦いが続いたかと思うと、右近は、右肩に激しい一突き受けて、「参りました。」と平伏したのでした。
家臣らの喝采に忠直卿は得意の絶頂にありました。祝宴になると寵臣たちは代わる代わる忠直卿の前に進み出て追従を述べます。祝宴の興が尽きかけた頃、忠直卿は座を発ちます。冷たい秋風の快さに、忠直卿はふと庭に下りてみたくなりました。
※追従(ついしょう) おべっかを使うこと。

小姓を一人連れて、庭に下り立った忠直卿は、静寂の中に身を置きます。そして小高い丘にある四阿で小半刻(約1時間)過ごしました。すると二人の人間が話しながら四阿の方へ近寄って来ます。彼らはそこに主君がいようとは夢にも気づいていないようです。
※四阿(あずまや) 東屋。庭園などに設けた四方の柱と屋根だけの休息所。
声の主は、今日白軍の大将を務めた小野田右近と副大将の大島左太夫でした。二人はどうやら紅白仕合について話しているようです。思わず忠直卿は二人の会話に耳を集中させてしまいます。
左太夫は声を潜めて右近に、「殿のお腕前をどう思う?」と聞きました。右近は、「御上達じゃ。」と答えます。左太夫が続けて、「以前ほど、勝ちをお譲りいたすのに、骨が折れなくなったわ。」と言うと、二人は苦笑している様子でした。

忠直卿は、生まれて初めて、土足をもって頭上から踏み躙られるような感情を持ちます。即座に両人を切って捨てようかとも思いました。しかし臣下から偽りの勝利を媚びられて得意になっていた自分が浅ましいとも思います。
傍に控えていた小姓は、二、三度小さい咳をします。はっとした二人は口をつぐむと、足早に去ってしまいました。忠直卿の瞳は怒りに燃え、その頬は凄まじいまでに蒼ざめています。右近の一言は彼の少年時代からの感情を見事に破産させてしまったのでした。
忠直卿は、今日の勝利の中でも、どこまでが本当で、どこからが嘘か分からなくなります。いや、生まれて以来幾度も試みた遊戯や仕合で、どれが本物でどれが嘘か分からくなりました。そればかりではなく、大坂の戦場で立てた偉勲、日本樊噲という称呼さえ誇張を伴っているように思えてきたのでした。
※偉勲(いくん) りっぱな手柄。大きな功績。
※称呼(しょうこ) となえ。呼び名。呼び方。なまえを呼ぶこと。
※誇張(こちょう) おおげさに表現すること。

翌日も忠直卿は、同様の槍術の大仕合を催します。忠直卿の瞳は爛々と燃えていました。紅軍は前日よりも不利でした。しかし忠直卿が出場すると、次々とその激しい槍先に突き伏せられてしまいます。次に現れたのは大島左太夫でした。
忠直卿は上ずった声で左太夫に、「真の腕前は真槍真剣でなければ分からない!そちも真槍をもって来い!主と思うに及ばぬ。隙があれば遠慮いたさずに突け!」と言い放ったのでした。左太夫、そして後ろに控えている小野田右近の顔色が変わります。
見物席にいる家中の者たちも忠直卿の心の内を解するのに苦しみました。忠直卿は、これまでは癇癖こそありましたが、このような非道無残な振舞いはなかったのです。忠直卿は、(真槍で戦うならわざと負けることもあるまい。そうすれば自分の真の力量が分かる)と思ったのでした。
※癇癖(かんぺき) 神経質で激しやすい性格。おこりっぽい性質。癇癪。

主君の振舞いを見ていた国老の本多土佐は、「殿!お気が狂われたか!」と、必死になって止めます。しかし忠直卿は、「止めだて無用じゃ!」と言い放ち、真槍を手にしました。昨夜の立話が殿の耳に入ったと考えた左太夫は、潔く主君に成敗されて死にたいと思いました。
「御免!」と叫びながら主君に立ち向った左太夫は、忠直卿の槍を左の股に受けて倒れます。しかし忠直卿の心には勝利の快感が少しもありませんでした。昨日と同じくわざと負けたことが分かったからです。左太夫が倒れると、次は右近の番です。
忠直卿は、右近だけは必死に戦うだろうと考えて立ち向かいました。しかし右近もまた潔く主君の長槍に突かれて自分の罪を謝そうとしていたのです。右近は忠直卿の突き出す槍先に故意に当てるようにして右の肩口を突かれます。
その夜遅く、忠直卿は、右近と左太夫が腹を裂いて死んだという知らせを受けます。忠直卿は、(自分と彼らとの間には虚偽がある)と考えました。しかしそれは必死の懸命の偽りです。その事実を考えると、忠直卿の心身に、苛々とした寂しさが襲ってくるのでした。

真槍の仕合があって以来、忠直卿の癇癖が一層と酷くなります。家臣たちは、今までにない心身の疲労を覚えるようになっていきました。忠直卿は、武術の稽古をしなくなります。そして酒杯を手にする日が多くなっていきました。
ある夜の酒宴の席のことです。珍しく機嫌が良かった忠直卿に、増田勘之介という小姓が酌をしながら、「殿、この頃兵法座敷に行きませぬが、御怠慢とお見受け申しまする。」と言いました。
すると、急に忠直卿の顔色は変わり、盃を勘之介の顔面に向けて投げつけたのでした。勘之介は白い顔から血を流しながら、その場に平伏します。勘之介は、その夜の明けるのを待たずに切腹しました。
※平伏(へいふく) ひれふすこと。両手をつき、頭を地や畳につけて礼をすること。

そのことがあってから十日ばかり経った頃です。忠直卿は、老家老の小山丹後と囲碁をしていました。三回続けて敗けた丹後は、「老人ではとても相手になり申せぬわ。」と言います。すると忠直卿は、いきなり立って碁盤を足蹴にしたのでした。
石は飛び散って丹後の顔を打ちます。急に怒り出した主君に向かって丹後は、「御乱心か。何故丹後にこのような恥辱を与えられる!」と狂気のごとくに叫びました。しかし忠直卿はそのまま奥へと去ってしまいます。
丹後は、幼年時代から育てあげた主君から、理不尽な辱めを受けたことを口惜しく思います。丹後は、わざと負けるなど卑劣な心など持っていませんでした。丹後は、その日家へ帰ると皺腹をかき切って命を捨ててしまったのでした。
※口惜しい(くちおしい) 残念だ。くやしい。

忠直卿の生活は、しだいに荒んでいき、酒食にふけり、色を漁るようになっていきます。国老の言うことも聞かなくなり、国政もおろそかになります。やがて、忠直卿乱行の噂は、江戸にまで知られるようになっていきました。
ある夜のことです。忠直卿は、愛妾たちと酒を飲んでいました。この頃忠直卿は、京都から来た絹野という愛妾を寵愛していました。その絹野が、連夜の酒宴に疲れ果てたのか、主君の御前にも関わらず、うつらうつらと、うたた寝をしていたのです。
この瞬間、忠直卿はまた新たな疑惑にとらわれてしまいます。(この女も自分に愛があるのではなく、主君という大権力者のために身を委しているに過ぎない。いや、この女ばかりでなく、今まで自分を心から愛した女が一人でもあっただろうか……)
忠直卿は、人間同士の人情を少しも味わわずに来たことに、この頃ようやく気がつき始めたのです。(彼らは友人として交わったのではなく、ただ義務感情から服従しただけなのだ……)
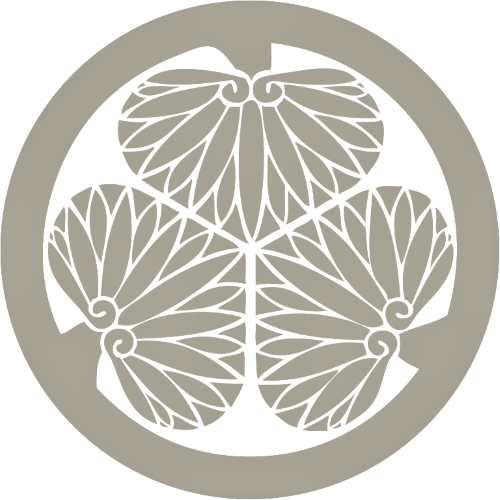
生活が荒むにつれて忠直卿は、義務や服従ではなくて、人間らしい反抗を示すような女性を愛したいと思うようになります。彼は家中の高禄の士に、娘を連れて来るように命じます。しかしその娘たちも、犠牲的な感情を持って忠直卿に接するだけでした。
次に忠直卿は、許嫁のある娘を物色します。夫の定まっている娘なら少しは反抗するだろうと思ったからでした。しかしこの娘たちも主君を絶対的なものとして祭り上げるだけでした。
忠直卿の乱行はなおも止まらず、今度は家中の者の女房三人を城に招き入れて、返さないといった非道な所業を犯します。夫から何度も嘆願されたものの女房は返されませんでした。重臣たちは忠直卿を、人倫の道に反する所業として強諫します。
※人倫(じんりん) 人間の秩序関係。転じて、人間の実践すべき道義。
※強諫(きょうかん) 強くいさめること。
女房を奪われた三人にうち二人が相次いで割腹(切腹)しました。そして家中の人々の興味は、妻を奪われながら、ただ一人生き残っている浅水与四郎に集まります。「腹を切らぬ臆病者」と非難する者までいたのです。

四、五日してから浅水与四郎は登城し、「忠直卿にお目通りを願いたい。」と申し出ます。目通りを許した忠直卿の前に、どことなく殺気を漂わせた与四郎が現れます。このとき忠直卿は生まれて始めて、自分の家臣が本当の感情を隠さず、顔に現わしてしるのを見たのでした。
「与四郎か!近う進め!」忠直卿は、与四郎に対して、一種の懐かしさを覚えます。畳の上を滑り寄った与四郎は、「殿!主従の道も、人倫の大道よりは小事でござるぞ。」と言いながら、忠直卿に飛びかかります。その手には匕首が光っていました。
※匕首(あいくち・ひしゅ) 短剣・懐剣の類で、また剣の最短なるものをいい、長さ一尺八寸ともいう。
ところが与四郎は、いとも簡単に忠直卿に捻じ伏せられてしまいます。忠直卿は、「余の家来には珍しい者じゃ。」と言い、哄笑します。与四郎は、「お手打ちを。」と嘆願しましたが、なんのお咎めもなく、妻も城から戻されたのでした。
※哄笑(こうしょう) 大口をあけて笑うこと。
忠直卿は大きな歓びを得ます。この勝負に嘘や偽りがあるとは思えなかったからでした。しかしこの歓びも長くは続きませんでした。与四郎夫婦が家に帰って直ぐに、枕を並べて覚悟の自殺を遂げてしまったからです。
.jpg)
二人の死を聞いた忠直卿は、再び疑念にとらわれてしまいます。(潔く手刃されるために与四郎は、匕首を握ったのではないか?もしもそうだとすると、紅白仕合のときと変わらないではないか……)
忠直卿の乱行は、その後益々進みました。家臣を手にかけるだけでなく、領民まで殺害するようになっていったのです。忠直卿に幕府から改易の沙汰が下されます。豊後国(現・大分市)へ配流となり、慶安3(1650)年9月10日に逝去します。享年56歳でした。
※改易(かいえき) 江戸時代、士分以上に科した刑罰。武士の身分を剝奪し、領地・家屋敷などを没収する刑。蟄居より重く、切腹より一段軽い。
忠直卿の晩年の生活について史実は伝わっていません。忠直卿警護の任に当たっていた豊後府内藩の家臣が、幕府の執政・土居利勝に送った「忠直卿行状記」の一冊があるばかりです。
そこには忠直卿のことを、「お慎み深く、近侍の者を憫れみ、領民を愛する有様、六十七万石の国を失った無法人とは見えずと人々不審く思う。」と書かれてありました。
青空文庫 『忠直卿行状記』 菊池寛
https://www.aozora.gr.jp/cards/000083/files/501_19864.html
『忠直卿行状記』の主人公・松平忠直(まつだいらただなお)について
.jpg)
松平忠直は、第2代将軍徳川秀忠の兄・結城秀康の長男として生まれます。慶長12(1607)年、父秀康の領地、越前国福井藩(現・福井県)32万石を相続します。元和元(1615)年の「大坂夏の陣」では真田幸村らを討ち取る大功をたてます。
しかしその後、恩賞の少なさに不満を抱き、酒色にふけり、残忍な行動がみられるといった評判がたちます。元和9(1623)年、藩政の乱れを理由に豊後萩原(現・大分市)へ配流となり、この地で慶安3(1650)年9月10日、逝去します。
『忠直卿行状記』【解説と個人的な解釈】
専門家のあいだでは、史実と違うといった意見もあるようですが、菊池寛は『忠直卿行状記』について、『文芸講座』「歴史小説論」の中で次のように述べています。
「忠直卿行状記」も、どちらかと云へば、実生活から題材を得た。私は、一人貴族の息子を知ってゐた。周囲の人の阿訣追従に依り、人生に対する正当なる認識を妨げられてゐるこの貴族の息子の存在から、私は「忠直卿行状記」を考へた。従って、忠直卿は私のテーマを小説化する道具である。忠直卿でも誰でもよかったのである。
(菊池寛『文芸講座』「歴史小説論」大正13年10月)
ちなみに阿訣追従とは、いわゆる “ ご機嫌とり ” のことです。つまり作者は、生まれながらにして絶対的な権力者という運命を背負わされた一人の人間の光の部分、そして闇の部分を、『忠直卿行状記』を通して描こうとしたようです。
当時まだ「華族制度」があり、貴族の中には忠直卿のような人物もいたでしょう。彼らは何の疑いもせずに権力を手にし、その権力で周りの人間を押さえつけていたと思われます。当然ながら主従のあいだに信頼関係など存在しません。あるのは「忠義」の一心です。
そんな人間は、疎外されていることに気づかず、権力を振りかざします。忠直卿の場合は疎外感に気づいたことで転落の人生を歩みます。とは言うものの晩年の生活を見る限り、権力の座に居座ることが果たして幸せなのか?といった疑問符がつきます。
明治大正と、欧米諸国から新しい文明が流れ込んできます。けれども日本にはまだ封建性が色濃く残っていました。もしかしたら作者は、忠直卿を封建制の犠牲者と見なしていたのかも知れません。
あとがき【『忠直卿行状記』の感想を交えて】
.jpg)
現代社会でも、生まれながらにして周りから殿様のように崇められて育つ人間がいると思います。代議士の子供、もしくは資産家の御曹司とかが例に上げられます。わたし自身そんな人間を何人か知っています。言うなれば「親ガチャ」に成功した人間たちです。
一方で彼らは「ボンボン育ち」と、妬み嫉み半分でしょうが陰口を叩かれたりしていました。けれども実際は人間的に優れた人物も見ています。つまり、どのような育てられ方をしたかが大事なのでしょう。
ともかくとして、忠直卿も大名の家にさえ生まれなければ、太宰が『水仙』で語っているように、芸事で「天才」の粋に達していたのかも知れません。なぜ疑問符がつくかと言うと、どうしても周りが色眼鏡をかけて見てしまうからです。
「あいつは恵まれてるから」その一言で努力さえも否定されてしまいます。とは言え、持たない者が持つ者を羨むのは当然です。かく言うわたしも、そんな立場に生まれたかったと羨む心貧しき人間なのだと『忠直卿行状記』を読んで再認識してしまいました……。




コメント