はじめに【「評論家」という肩書】
様々なメディアで○○評論家という肩書の人を良く見かけます。評論対象は文学、政治、経済、言語、科学、技術、そして遊びや趣味などで、基本的には特定の分野だけを評論の対象としています。
けれども、その評論対象は専門分野を飛び越えることもあり、ときには意見の違う者同士で罵倒し合ったり、果てには訴訟問題にまで発展するなんてことも・・・。
文芸評論の草分け的存在とも言える小林秀雄はこのように書き残しています。
「自分の仕事の具体例を顧みると、批評文としてよく書かれているものは、皆他人への賛辞であって、他人への悪口で文を成したものはない事に、はっきりと気附く。そこから率直に発言してみると、批評とは人をほめる特殊の技術だ、と言えそうだ。人をけなすのは批評家の持つ一技術ですらなく、批評精神に全く反する精神的態度である、と言えそうだ」
小林秀雄『無常という事』要約と解説【常なることを見失った!】
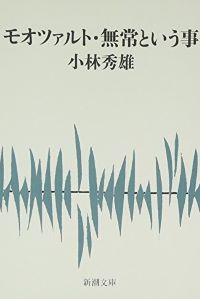
小林秀雄(こばやしひでお)とは?
小林秀雄は昭和期に活躍した日本の文芸評論家、編集者、作家、美術・古美術収集鑑定家です。(1902-1983)小林は明治35(1902)年、東京市神田区(現:東京都千代田区神田)猿楽町に生まれます。
東京府立第一中学校(現:日比谷高等学校)、第一高等学校と進み、大正14(1925)年4月、東京帝国大学文学部仏蘭西文学科に入学します。在学中に中原中也や大岡昇平と知り合います。卒業後は志賀直哉家に出入りするようになります。

志賀直哉『城の崎にて』【生かされていることに感謝!】
志賀直哉『小僧の神様』【偽善心と埋められない格差の溝!】
志賀直哉『清兵衛と瓢箪』【型に嵌めたがる社会への批判!】
志賀直哉『焚火』【子を想う母と母を想う子の不思議な交感!】
昭和4(1929)年9月、『改造』の懸賞評論第二等入選作『様々なる意匠』で文壇に登場します。翌年から『文芸春秋』に文芸時評を連載し、批評家としての地位を確立します。
昭和8(1933)年10月、川端康成らと『文學界』の創刊に参加します。昭和10(1935)年からは編集責任者となり『ドストエフスキイの生活』を連載し始めます。戦争末期から戦争直後にかけて『無常といふ事』『モオツアルト』などの話題作を発表していきます。
その後も『ゴッホの手紙』『近代絵画』『考へるヒント』や大著『本居宣長』を発表していきます。昭和58(1983)年3月1日、腎不全のため死去してしまいます。(没年齢80歳)

『無常という事』【要約!】
本文の冒頭は、鎌倉時代の法談集『一言芳談抄』を引用しています。
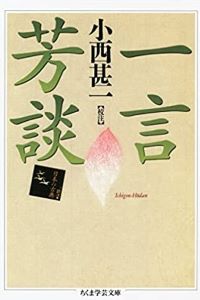
(原文)
或云、比叡の御社に、いつはりてかんなぎのまねしたるなま女房の、十禅師の御前にて、夜うち深け、人しづまりて後、ていとうていとうと、つづみをうちて、心すましたる声にて、とてもかくても候、なうなうとうたひけり。
其心を人にしひ問はれて云、生死無常の有様を思ふに、此世のことはとてもかくても候。なう後世をたすけ給へと申すなり。云々。
(『一言芳談抄』)
比叡の御社 = 現在の日吉大社(滋賀県大津市)
なま女房 = 若い女房
十禅師 = 日吉山王七社権現の一つ
(現代語訳)
ある人が言った。比叡の御社で、偽って巫女のいでたちをした若い女房が、十禅師の御前において、夜がとっぷりと更け、人も寝静まってから、たぁーんたぁーんと鼓を打って、澄みわたった声音で、どうでもいいことでございますよねえ、そうでしょう、ねえねえ? と謡っていた。
その気持を人から詰問されて答えたことには、生死無常のありさまを思えば、この世のことはどうでもよい、ただ後の世のことをお助け下さいと申し上げたのです、とのことであった。
一言芳談(いちごんほうだん)
出典:精選版 日本国語大辞典
浄土各流の高僧中、法然、聖光、良忠、貞慶など二十余師の法語百六十余を雑然と集めたもの。一巻本、二巻本、三巻本があるが、一巻本が原型とされる。編者不明。鎌倉後期の作といわれる。

小林はこの『一言芳談抄』の中にある文を、「読んだ時、いい文章だと心に残った」と述べ、比叡山に行ったとき、「突然、この短文が、当時の絵巻物の残欠でも見る様な風に心に浮び、文の節々が、まるで古びた絵の細勁な描線を辿る様に心に沁みわたった。」と語ります。
※残欠(ざんけつ) 書物などの、一部分が欠けていて不完全なこと。
※描線(びょうせん) かたちをえがいた線。
そのときの事を回想しながらも小林は、「実は、何を書くのか判然しないままに書き始めている。」と述べ、「あれほど自分を動かした美しさは何処に消えて了ったのか?」と、自らに問いかけ、そんな疑問が「僕を途方もない迷路に押しやる。」と語ります。
そして、それに対し「反抗はしない。」と言い、「そういう美学の萌芽とも呼ぶべき状態に、少しも疑わしい性質を見付け出す事が出来ないからである。」とその理由を語ります。けれども小林は、「僕は決して美学には行き着かない。」と、前言とは真逆のことを述べます。
※萌芽(ほうが) 芽がもえ出ること。めばえ。転じて、物事のはじまり。きざし。

更に小林は、「自分が生きている証拠だけが充満し、その一つ一つがはっきりとわかっているような時間。」を思い出しているだけと語り、「鎌倉時代をか。そうかも知れぬ。そんな気もする。」と述べ “ 歴史の解釈論 ” へと展開します。
そして晩年の森鷗外を持ち出し、「あの膨大な考証を始めるに至って、彼は恐らくやっと歴史の魂に推参したのである。」と述べ、「本居宣長の『古事記伝』を読んだ時も同じ様なものを感じた。」と語ります。
※推参(すいさん) 自分の方から押しかけて参上すること。
小林は、「解釈を拒絶して動じないものだけが美しい、これが宣長の抱いた一番強い思想だ。解釈だらけの現代には一番秘められた思想だ。」と語り、ある日、川端康成に言ったという言葉を思い出します。
.jpg)
(原文通り)
生きている人間などというものは、どうも仕方のない代物だな。何を考えているのやら、何を言い出すのやら、仕出来すのやら、自分の事にせよ他人事にせよ解った例しがあったのか。鑑賞にも観察にも堪えない。
其処に行くと死んでしまった人間というものは大したものだ。何故、ああはっきりとしっかりとして来るんだろう。まさに人間の形をしているよ。してみると、生きている人間とは、人間になりつつある一種の動物かな。
そして小林は、「歴史には死人だけしか現れて来ない。動じない美しい形しか現れぬ。」と述べ、「僕らが過去を飾り勝ちなのではない。思い出が、僕等を一種の動物である事から救うのだ。」と語ります。

更に小林は、記憶するだけでは駄目で思い出す必要があるとし、「多くの歴史家が、一種の動物に止まるのは、頭を記憶で一杯にしているので、心を虚しくして思い出す事が出来ないのではあるまいか。」と自分の考えを述べます。
(以下原文通り)
上手に思い出す事は非情に難しい。だが、それが、過去から未来に向かって飴の様に延びた時間という蒼ざめた思想(僕にはそれは現代における最大の妄想と思われるが)から逃れる唯一の本当に有効なやり方の様に思える。成功の期はあるのだ。
この世は無常とは決して仏説という様なものではあるまい。それが幾時如何なる時代でも、人間の置かれる一種の動物的状態である。現代人には、鎌倉時代の何処かのなま女房ほどにも、無常という事がわかっていない。常なるものを見失ったからである。」
『無常という事』【解説と個人的な解釈】
「無常」という言葉は仏語ですが、主に「生命のはかなさ」を表す言葉として使われます。作者は比叡山に行った際、『一言芳談抄』のなま女房の話を思い出し「無常」について考察していきます。
とは言うものの、「何を書くのか判然しないままに書き始めている。」と語っているように、作者が自らの思うがまま、考えを述べていっているところが本作品を一層理解しにくくしている点と言えるでしょう。
小林は、まるで自分の考えを整理するかのようにペンを進めていきます。そして導き出したのは、「生きている人間は、人間になりつつある一種の動物」という答えです。また「思い出」が人間を、「一種の動物である事から救うのだ。」と語ります。
ここで小林は、「思い出」の対比として「記憶」を持ち出し、「多くの歴史家の頭が記憶で一杯になり、心を虚しくしているのではないか?」といった自論を述べます。
少し横道に逸れますが、小林は随筆『文章について』で、「評論の文章がただ理路の通った文章に止まらず、魅力ある生きた文章たることを期するといふ点にある。」という言葉を残しています。
つまり、「記憶=知識」よりも「思い出=感動」が大事なのだと、当時の歴史家(評論家)達への皮肉も込められているような気もします。いや、小林の眼には当時の現代人が一様に「一種の動物的状態」に見えたのかも知れません。
最後は、「現代人には(中略)無常という事がわかっていない。常なるものを見失ったからである。」と結ばれますが、その「常なるもの」とは果たして何なのでしょうか。個人的には「古来からの信仰」、つまりは森羅万象に対する「敬う心」のような気がしてなりません。
あとがき【『無常という事』の感想を交えて】

『無常という事』には多くの比喩表現が登場します。ですからこの作品を「散文詩」として捉えている専門家もいます。わたし自身、以前読んだとき理解に苦しみましたが「散文詩」として読むことで多少は胸に落ちてきたような気がします。
そもそも小林本人が、「解釈を拒絶して動じないものだけが美しい。」と言っているのですから理解すらする必要がないのかも知れません。頭で考えるよりも心で受け止める作品とでも言いましょうか。
ともかくとして、なま女房の言葉には小林同様、わたし自身も心に響くものがあります。「無常」そのものの現世で、自分が優位に立つことでそれが何になるのでしょう。それよりも他者を慈しんでいたほうがどんなに楽でしょうか。
小林の考えに沿うと、意見の違う人を認めず攻撃ばかりしている識者や批評家は、「常なることを見失っている」―――と言えるのかも知れません。




コメント