はじめに【夏の風物詩「怪談」】
夏の風物詩のひとつとして「怪談」を連想する方が多いと思います。わたし自身も少年の頃から好んで怪談物を読み、決まって夜になると一人ではトイレに行けなくなるといった苦い経験をしてきました。
ましてや夏には、「お盆」という日本人には欠かせぬ年中行事があり、お盆期間にはあの世から死者の霊魂が帰ってくるとされているのですから、その恐怖心たるや少年にとって相当なものでした。
お墓参りのときなどは仮病を使って逃れようともしました。結局は叱られながら恐る恐る行くことになるわけですが、何故そんなにまでお墓参りを拒んだかと言うと、小泉八雲の『耳無芳一の話』が少年の胸に深く刻まれていたからです。
小泉八雲『耳無芳一の話』あらすじ【『平家物語』安徳天皇の入水!】

小泉八雲(こいずみやくも)とは?
小泉八雲(イギリス名:ラフカディオ=ハーン(Lafcadio Hearn))は、明治時代の英文学者・随筆家・小説家です。(1850-1904)
小泉八雲はギリシアに生まれ、生後1年半でアイルランドに移り、のちに渡米して新聞記者となります。明治23(1890)年に来日し、島根県の松江中学に赴任します。同年小泉セツと結婚し、日本に帰化します。

その後、熊本の第五高等学校、東京帝国大学、早稲田大学の教壇に立ちます。この間、『知られざる日本の面影』『心』『仏の畑の落穂』を出版し、日本の風土と心を海外に紹介します。
その一方、『古今著聞集』などの古典や民間説話に取材した創作集『怪談』を発表し、物語作者としての才能も発揮します。明治37(1904)年9月26日、狭心症のため死去します。(没年齢:満54歳)

小泉八雲『雪女』あらすじ【『遠野物語』他各地の雪女の伝承!】
怪談『耳無芳一の話』について

『耳無芳一の話』は明治37(1904)年、小泉八雲が著した怪奇文学作品集『怪談』(英:Kwaidan)に収録されます。八雲は、妻の節子から日本各地に伝わる伝説、幽霊話などを聞き出して、文学作品としてよみがえらせます。
ちなみに、17編の怪談を収めた『怪談』と3編のエッセイを収めた『虫界』の2部からなっています。
『耳無芳一の話』あらすじ(ネタバレ注意!)

何百年か昔のことです。赤間ヶ関(現代の下関)に、芳一という盲目の琵琶法師が住んでいました。芳一の琵琶の弾き語りは、少年の頃から師匠たちを凌駕し、源平の物語を吟誦するのが特に上手で、「壇ノ浦の戦い」の歌を謡うと「鬼神も涙を流す」と言われたほどでした。
※凌駕(りょうが) 他のものを越えてそれ以上になること。
※吟誦(ぎんしょう) 詩歌を、声をあげ節をつけてよむこと。
琵琶法師として駆け出しの頃の芳一はとても貧乏でした。けれども芳一の技量にひどく感心した阿弥陀寺の住職が、寺院の一室を提供し、食事まで与えると言い出したのです。芳一は有り難くその申出でをお受けし、その返礼として用事のない晩には琵琶を弾いて、住職をお慰めすることとなったのでした。
ある夏の夜の事です。住職は法事に出かけ、寺には芳一ひとりが残されました。芳一は縁側で琵琶を弾いて、寂しさを紛らわしていたのですが、そのとき裏門から近づいてくる足音が聞こえてきます。けれどもそれは住職ではありませんでした。

「芳一!」と、侍のような低い声が盲人の名前を呼んだのです。芳一は怯えながらも「はい」と返事をし、「私は目が見えませぬ。―――私をお呼びの方はどなた様でございますか?」と、訊ねたのでした。
すると声の主は、「“ 高貴なお方 ” が赤間ヶ関に御滞在なされていて、是非ともそのほうの演奏を聞きたいと所望されている。であるから、琵琶を持ち即刻拙者と来るが良い。」と、言うのです。当時侍の命令は絶対で、芳一はその申し出に従うことにしました。
芳一は、侍の導かれるままに道を急ぎます。そして大きな門をくぐり、広い邸内を通り抜けて、大きな部屋の真ん中へと案内されました。盲目の芳一にはよく分かりませんでしたが、大勢の人の話し声が聞こえます。その言葉は宮中の言葉のようでした。
やがて女中頭と思われる老女が現れ、芳一に向かって、「平家物語の壇ノ浦の戦いの話を語っていただきたいという御所望に御座います。」と言います。芳一は声を張り上げて、激しい海戦の歌を吟誦しました。

芳一の演奏に、聴衆は皆熱心に聴き入り、その演奏の途切れ途切れに、人々は賞賛の声を上げます。けれども語りが佳境になり、幼帝を両腕に抱いたまま入水した二位の尼の吟誦に入ると、聴衆は皆、激しくむせび泣いたのでした。
演奏を終えた芳一に、女中頭と思われる老女がこう言います。
「殿様は大層お気に召しています。これから後六日の間、毎晩一度ずつ殿様の御前で演奏をお聞き入れるよう。ただしこの事は一切口外致さぬようにとの御上意によります。」
芳一は、約束通りにこの不思議な出来事を誰にも口外せず、翌日も “ 高貴なお方 ” の所へ行き演奏をしました。ところが住職は、目の見えない芳一が無断で寺から抜け出していることに気が付き、そのことを芳一に問い質します。けれども芳一は黙ったままでした。
そこで不審に思った住職は翌晩、寺の下男たちに芳一の後を着けさせます。すると下男たちは、阿弥陀寺の墓地の中、大雨にもかかわらず、一心不乱に琵琶を掻き鳴らす芳一の姿を見つけたのでした。近づくとそこは安徳天皇の記念の墓前です。そして芳一の周りには恐ろしいほど無数の鬼火が燃えていました。
※下男(げなん) 男の召使。下僕。しもべ。
※鬼火(おにび) 日本各地に伝わる怪火(空中を浮遊する正体不明の火の玉)のこと。

その様子に驚いた下男たちは、強引に芳一を寺へと連れ帰ります。住職は芳一にこの晩の出来事を教え、打ち明けるようにと迫ります。芳一は長い時間躊躇しましたが、とうとう住職に一切合切を物語ったのでした。
芳一が、平家一門の邪悪な怨霊に憑りつかれていることを知った住職は、(このままでは怨霊に殺されてしまう)と、芳一の身を案じます。そこでこの晩、法会に行くことになっていた住職は芳一の身を守るため、芳一の身体中に経文を書くことにしました。
※法会(ほうえ) 経典を読誦し、講説する催し。また、死者の追善供養を営む行事。
住職は芳一を裸にし、弟子の僧侶とともに身体中の隅々まで、般若心経というお経を書きつけて、「どんな事があっても決して恐がらず、動いたり音を立ててはいけない。私の言う通りにしておれば、間違いなく危険は通り過ぎるであろう。」と、堅く言い含めたのでした。

その晩のことです。「芳一!」と低い声がし、いつものように侍の怨霊が芳一を迎えに来ます。けれども経文の書きつけられた芳一身体は、怨霊の目には見えません。怨霊は何度も芳一の名を呼びますが、芳一は住職の申しつけに従い、決して物音のひとつも立てず、じっとしていました。
当惑した怨霊は芳一を探し回ります。そして縁側の上に琵琶と両耳を見つけます。怨霊は、「返事をする口がないのだ。両耳の他、琵琶師の体は何も残っておらん。ならば証拠として、この耳を持ち帰る他あるまい。」と言い、芳一からその両耳を引きちぎったのでした。

芳一を激しい痛みが襲います。それでも芳一は身動きひとつせず、声も上げませんでした。怨霊はそのまま去って行きます。―――明け方に帰って来た住職は、血だらけになった芳一の姿に驚きます。芳一から昨夜の一部始終を聞いた住職は、耳にだけ経文を書き漏らした自分の手落ちを後悔し、その非を芳一に深く詫びたのでした。
その後、平家の怨霊は二度と現れず、芳一の耳の傷も無事に癒えます。この不思議な出来事は世間に広まり、芳一の琵琶の吟誦はたちまち有名になりました。結果的に名声を高め、多くの富を得るようになった彼は「耳なし芳一」と呼ばれるようになったのでした。
青空文庫 『耳無芳一の話』 小泉八雲 戸川明三訳
https://www.aozora.gr.jp/cards/000258/files/42927_15424.html
『平家物語』【「壇ノ浦の戦い」先帝身投(安徳天皇の入水)!】
『平家物語』(へいけものがたり)について
『平家物語』とは、鎌倉時代前期に書かれた軍記物語のことです。作者は不詳とされていますが、吉田兼好は『徒然草』の中で、作者として後鳥羽院時代の信濃前司行長の名をあげていて、この説が有力とされています。
平氏の栄華と没落を主題としていて、「祇園精舎の鐘の声……」で始まる冒頭文は広く知られています。平曲として琵琶法師によって語られたことで広く愛好され、後世の文学に大きな影響を与えます。
※平曲(平曲) 『平家物語』を琵琶の伴奏で語る音曲のこと。
「壇ノ浦の戦い」【先帝身投(安徳天皇の入水)】
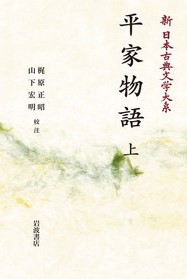
「壇ノ浦の戦い」は、元暦2/寿永4(1185)年に下関市東方の壇之浦で行われた源平最後の海戦のことです。屋島の戦いに敗れた平氏は長門彦島(下関市)を拠点とし、500余艘の兵船をもって、源義経率いる840余隻の船団を迎撃しようとします。
開戦当初は潮流にのった平氏方が有利でしたが、途中から逆潮となり劣勢に立たされます。平氏軍の敗北を悟った平氏一門の武将たちや女性たちは次々と入水していきます。安徳天皇と二位尼も同じ運命をたどりますが、『平家物語』ではこの場面を次のように記しています。

先帝身投(原文)
二位殿は、この有様を御覧じて、日頃思し召し設ける事なれば、鈍色の二つ衣うち破き、練袴のそば高く挟み、神璽を脇に挟み、宝剣を腰に差し、主上を抱きたて奉つて、「わが身は女なりとも、敵の手にはかかるまじ。君の御供に参るなり。御志思ひ参らせ給はむ人々は急ぎ続き給へ。」とて、船端へ歩み出でられけり。
(現代語訳)
二位殿(安徳天皇の祖母、平清盛の妻・時子)はこの有様を御覧になって、普段から覚悟しておられたことなので、濃い灰色の二枚重ねの衣をかぶり、練絹の袴のそばを高く挟んで(すそを上げ)神璽を脇に抱え、宝剣を腰に差し、安徳天皇をお抱き申し上げて、「私自身は女であるけれども、敵の手にはかかりません。陛下のお供に参るのです。志をお通し申し上げなさる人々は、急ぎ、お続き下さいませ。」と言って、船端に歩み出られた。
(原文)
主上今年は八歳にならせ給へども、御年のほどよりはるかにねびさせ給ひて、御形美しく、辺りも照り輝くばかりなり。御髪黒うゆらゆらとして、御背中過ぎさせ給へり。あきれたる御有様にて、「尼前、我をばいづちへ具して行かむとするぞ。」と仰せければ、いとけなき君に向かひ奉り、涙を抑へて申されけるは、
(現代語訳)
安徳天皇は、今年は八歳におなりになったけれども、ご年齢のわりにははるかに大人びていらっしゃって、ご容貌は美しく、あたりも照り輝くほどである。御髪は黒くゆらゆらとしていて、御背中の下まで長く伸びていらっしゃった。安徳天皇は驚かれた御様子で、「尼さま、私をどこへ連れて行こうとしているのか。」とおっしゃったので、(祖母の二位殿が)幼い天子にお向かい申し、涙を抑えて申されたことは、
(原文)
「君はいまだ知し召されさぶらはずや。先世の十善戒行の御力によつて、今万乗の主と生まれさせ給へども、悪縁にひかれて、御運すでにつきさせ給ひぬ。まづ東に向かはせ給ひて、伊勢大神宮に御暇申させ給ひ、その後、西方浄土の来迎のあづからむと思し召し、西に向かはせ給ひて御念仏さぶらふべし。この国は粟散辺地とて心憂き境にてさぶらへば、極楽浄土とてめでたき所へ具し参らせさぶらふぞ。」
(現代語訳)
「陛下はまだご存じないのでございましょうか。前世での十善戒行のお力によって、今万乗の君主(=天皇)としてお生まれなさっておられますけれども、悪縁に引かれて、ご運は尽きてしまわれました。まず東にお向きになられて、伊勢大神宮へお別れを申し上げなさり、その後、西方浄土の仏によるお迎えをお受けしようとお思いになり、西にお向きになって御念仏をお唱えください。この国は粟散辺地といって、不快な場所でございますので、極楽浄土という素晴らしい所へお連れ申すのです。」
※粟散辺地(ぞくさんへんじ) 辺地にある、あわ粒を散らしたような小国。
(原文)
と泣く泣く申させ給ひければ、山鳩色の御衣に、角髪結はせ給ひて、御涙におぼれ、小さくうつくしき御手をあはせ、まづ東を伏し拝み、伊勢大神宮に御暇申させ給ひ、その後西に向かはせ給ひて、御念仏ありしかば、二位殿やがていだきたてまつり、「浪の下にも都のさぶらふぞ。」となぐさめたてまつつて、千尋の底へぞ入り給ふ。
(現代語訳)
と、泣く泣く申されたので、山鳩色の御衣に、角髪をお結いになられて、お涙をたくさんお流しになり、小さくかわいらしいお手を合わせて、まず東を伏し拝み、伊勢大神宮にお別れを申し上げられ、その後、西にお向かいなさって、お念仏をお唱えになったので、二位殿はそのまま(安徳天皇を)お抱き申し上げ、「波の下にも都がございますよ。」とお慰め申して、深い海の底へお入りになった。
※角髪(みずら) 上代の成人男子の髪の結い方。髪を頭の中央から左右に分け、両耳の辺りで先を輪にして緒で結んだもの。平安時代以後、主として少年の髪形となった。びんずら。びずら。
あとがき【『耳無芳一の話』の感想を交えて】

たった一度だけですが下関に行き、「壇ノ浦の戦い」に思いを馳せたことがあります。戦の習いとは言え多くの人々がこの海(下関海峡)で命を落としたのですから複雑な気持ちでした。
『平家物語』は「壇ノ浦の戦い」から数十年後には原型が形づくられていたとされています。ですから当時の人々にとってはそう遠くない出来事で、琵琶法師の弾奏とともに語られる平家一門の悲劇は、人々の涙を誘ったことでしょう。
いや、当時の人々のみならず、今もなお文学作品として影響を及ぼし続けているのですから、凄いとしか言いようがありません。そして『平家物語』から波及し、『耳無芳一の話』という作品が生まれました。
『耳無芳一の話』が少年期のわたしを恐怖に陥れたことは冒頭で書きましたが、万が一に備えて、般若心経の写経を一心不乱にしていたことは秘密です。




コメント