はじめに【「女子挺身隊」について】
戦時下に置かれていた日本政府は、昭和13(1938)年に「国家総動員法」を公布し、若年層にまで勤労奉仕を強いるようになります。その後太平洋戦争が勃発し、昭和18(1943)年に入ると学徒の「勤労動員」が始ります。
約90万人の学徒が軍需工場等に徴用されることになりますが、同年9月には、14歳から25歳までの、未婚・無職・不在学女子に対し、一年ないし二年の長期にわたる勤労奉仕が義務づけられます。
この勤労動員組織は「女子挺身隊」と名付けられました。昭和19(1944)年6月からは年齢が12歳にまで引き下げられます。掌編小説『十七歳』は、そんな時代を生きた一人の少女が主人公となっています。
川端康成『十七歳』あらすじと解説【イヤデスと言えない苦しみ!】
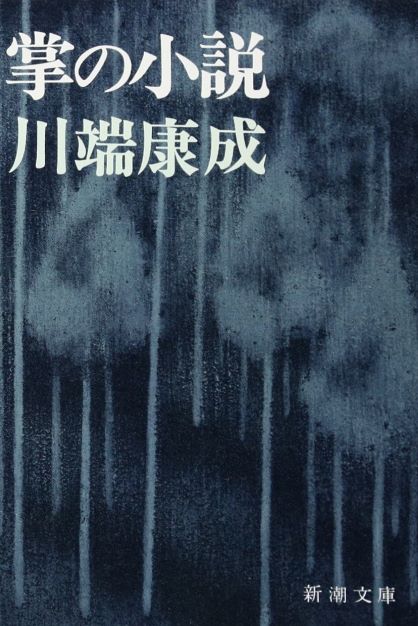
川端康成(かわばたやすなり)とは?
川端康成は、大正から昭和の戦前・戦後にかけて活躍した近現代日本文学の頂点に立つ作家の一人です。(1899~1972)
明治32(1899)年、大阪市北区で医師を務める川端栄吉の長男として誕生しました。幼い頃に両親を亡くし、母方の祖父母の手によって育てられます。成績も優秀であった川端は早くから作家を志します。
第一高等学校(旧制一高)から東京帝国大学国文学科(東京大学文学部)へと進み、創作活動を始めます。またこの頃、菊池寛に認められ、多くの作家の知己を得ます。

菊池寛『藤十郎の恋』【女遊びは芸の肥やしと言うけれど・・・】
帝大卒業後は、新感覚派作家として独自の文学を貫き、流行作家へと階段を駆け上っていきます。やがてその文学性は国際的にも認められるようになり、昭和43(1968)年には、ノーベル文学賞を受賞しました。
そんな栄光溢れる川端の作家人生でしたが、思いがけない形で突如終わりを迎えます。昭和47(1972)年4月16日、逗子の仕事部屋でガス自殺をしてしまいます。なお、遺書はありませんでした。(享年・72歳)
著書には『伊豆の踊子』『雪国』『古都』『山の音』『眠れる美女』など、日本文学史に燦然と輝く名作が多数あり、その輝きは現代でも失われていません。
.jpg)
川端康成『伊豆の踊子』あらすじ【文豪もやっていた自分探し!】
川端康成『雨傘』『木の上』あらすじと解説【甘酸っぱい恋物語!】
川端康成『ざくろ』あらすじと解説【きみ子の秘密の喜び!】
川端康成『日向』あらすじと解説【失った家族への憧れと希望!】
掌編小説『十七歳』について
『十七歳』は『わかめ』『小切』と併せて、昭和19(1944)年7月発行の『文芸春秋』に、『一草一花』という総題のもとに発表されます。その翌年に『朝雲』(新潮社)に収録されます。
「掌の小説」(たなごころのしょうせつ)について
※(てのひらのしょうせつ)とルビが付されている場合もあります。
川端康成は戦前戦後を通して一連の短い作品を書いています。その総数は128編ほどになるといわれ、これらも作品群を川端は「掌の小説」と名付けています。つまり掌に書きつけた小説とか、掌に入ってしまうささやかな小説ともうけとられます。
初期の頃の35編は大正15(1926)年6月15日に金星堂より刊行の処女作品集『感情装飾』に初収録されます。その後の昭和5(1930)年4月7日に新潮社より刊行の『僕の標本室』には、新作を加えた47編が収録され、昭和13(1938)年7月19日に改造社より刊行の『川端康成選集第1巻』には77編が収録されました。

改造社版『川端康成選集』第一巻のあとがきで作者自らこのように言っています。
私の旧作のうちで、最もなつかしく、最も愛し、今も尚最も多くの人に贈りたいと思ふのは、実にこれらの掌の小説である。この巻の作品の大半は二十代に書いた。多くの文学者が若い頃に詩を書くが、私は詩の代りに掌の小説を書いたのであつたらう。
無理にこしらえた作もあるけれどもまたおのづから流れ出たよい作も少なくない。今日から見るとこの巻を『僕の標本室』とするには不満はあつても若い日の詩精神はかなり生きてゐると思ふ。
けれども十二年後の全集で作者はこの評価をくつがえしています。
こんどこの全集のためにこれらの掌の小説を読みかへしてみて、私は 『最も愛し』てゐると言ふことはためらはれ、『若い日の詩精神はかなり生きてゐる』と言ふことにも疑ひを持つた。
と、川端康成は言うものの、作家の手を離れ読者のものとなった作品は、今でも一人一人の心に寄り添い続けています。
『十七歳』あらすじ(ネタバレ注意!)

「銀杏が落ちているから!」と姉は妹に誘われてお寺の庭に行きました。すると、お寺の地蔵堂には、「ここで遊んではいけません。」と貼り紙がしてあります。けれども良く見るとその横に黒い鉛筆で、「イヤデス。」と書かれていました。それを書いたのは妹だったのです。
姉はあわてて妹を連れ帰りました。その時以来、「イヤデス。」というのが妹の愛称のようになります。妹が何か都合の悪いことで渋っていると「イヤデス。」と横から姉が言い、母までもが「イヤデス。」とからかったりしました。そのうち妹は「イヤデスさん。」と呼ばれるようになります。
けれどもこれは十年前のことで妹は今、入院をしています。病気をしてからの妹は些細なことにも涙脆くなり、感傷的になっては、昔のことを思い出しました。ですから、姉に出す手紙には、「イヤデスより。」と書こうと考えています。
.jpg)
夜になると、人々の寝静まった町が感じられ、自分一人だけが時間の外に置き去られたような気がします。妹は呟きます。「もうみんな眠っている。みんな愛してあげる。」そして、戦争中なのに病人として休んでいる自分を思うと、涙が出てくるのでした。
ある日、姉が見舞いにやって来ます。姉は妊娠していました。お兄さん(姉の旦那)は兵隊として沖縄に行っています。姉は、「お母さまから頂いて来たの。」と言い、大きい風呂敷包みの結び目をゆっくりと解きます。
それは、―――四歳で亡くなった、上の姉の晴着でした。
母は上の姉のことを、自分の心の奥に仕舞いこんでいました。けれども姉と妹はそのことに薄々気付いていました。そしていつからか、この晴れ着は姉妹にとても大事なものとなっていたのです。

妹は、「でも、男の子か女の子か分からないでしょう。」と言いますが、姉は、「女の子らしいわ。」とあっさり答えます。妹は「そんな死んだ人の着物着せていいの?」と食い下がりますが、その一方で、姉を妬んでいるような自分にびっくりしたのでした。
そんな妹に姉は、「今度赤ん坊にこの着物を着せてくるかもしれないわ。それまでに丈夫になってらっしゃいね。」と言い、「お母さまが、これを孫に着せておくれたら、きっとあの子もたっしゃになるでしょうって。ありがたいものよ。」と、話したのでした。
妹の眼に泪が溢れてきます。母や姉の愛情を考えると、悲しくなると同時に心が洗われていくような気がします。そして、(義兄も生まれる子供もみんなきっと護ってあげる)と、遠くへ掌を合わせる気持ちになり、生き生きとありがたく思うのでした。
『十七歳』【解説と個人的な解釈】

妹は、お寺の貼り紙に「イヤデス。」と書くような、無邪気そのものとも言える子供でした。けれどもそんな妹も、病床に伏しているうちに情緒が不安定になっていきます。病院の一室といった外の世界から遮断された空間が、妹の「孤独」を増幅させていきます。
それはまるで、自分一人だけが時間から取り残されたかのようです。ですから過去を思い出して見ては感傷的になるしかないのです。と同時に「時代」が妹を追い詰めていったとも言えるでしょう。
本ブログの冒頭で「女子挺身隊」について書きましたが、「時代」は女子の労働力を必要としていました。つまり戦時下にも関わらず、お国の力になれないでいる自分自身をも嘆いているのです。
そんな妹のところに姉が見舞いに来て、四歳で亡くなった、上の姉の「晴着」を見せます。「晴着」は姉妹が共有していた大切な思い出の一部でした。ですから母から「晴着」を貰った姉に対し、嫉妬心のような不思議な感情を抱きます。また健康な姉へと羨望もありました。
けれども、その「晴着」には、母や姉の、妹への「愛情」が込められていたのです。妹は自分の嫉妬心を恥ずかしく思います。その瞬間から〈思い出〉だった「晴着」は〈未来への希望〉へと変わります。
妹は心の底から願います。―――(早く戦争が終わり、姉から生まれてくる子供が「晴着」を着られる、平和な世の中になりますように)と。
あとがき【『十七歳』の感想を交えて】

自分自身、どのような「十七歳」を過ごしていたかと考えると、「幸せだったなあ。」としみじみ実感します。現在と同様に貧富の差はあったものの「戦争」とは無縁の時代を過ごしてきたからです。
「戦争」はわたしたちの生活から全てを奪います。言論までも封じられてしまいます。つまり「イヤデス。」というたわいもない一言までも奪われてしまうのです。わたしがとやかく言うまでもなく、目の前で起きている「戦争」を見てもそれは明らかでしょう。
『十七歳』は、昭和19(1944)年7月という戦争末期の、いわゆる厳しい言論統制のなか発表されます。ですから文豪・川端康成と言えども正面切って「戦争反対」とは唱えていません。けれども、平和への願いがひしひしと感じられる物語となっています。
ともかくとして、わたしたちは「イヤデス。」と言える時代に生きていることに感謝しなければならないようです。




コメント