はじめに【「鬼子母神」の神話】
法華経(日蓮宗・法華宗)の寺院で祀られている仏教の神に「鬼子母神」という神様がいます。この鬼子母神、当初の名は鬼子母と言い、一万人(五百人、千人の説もある)の子の母でした。
鬼子母は、これらの子を育てるために栄養をつけようと、人間の幼児を奪って食べていました。そんな行為を見かねた釈迦は鬼子母の一子を隠します。鬼子母は半狂乱になって我が子を探し回りましたが見つかりませんでした。
悲嘆に暮れた鬼子母は助けを求めて釈迦に縋ります。そこで釈迦は、「子を失う悲しみは、鬼子母が食べた子の母の悲しみである。」と諭しました。鬼子母は釈迦に教えを請います。そして仏に帰依すると誓った鬼子母の元に、釈迦は隠していた子供を戻したのでした。
こうして鬼子母は善神へと生まれ変わり、子授け・安産・子育ての神「鬼子母神」として祀られるようになったと云われています。このとき釈迦が、「再び子供を食べたくなったときは、人肉に味が似ている柘榴を食べなさい。」と言われたという俗説があります。
果たして石榴は本当に人肉と味が似ているのでしょうか?
川端康成『ざくろ』あらすじと解説【きみ子の秘密の喜び!】
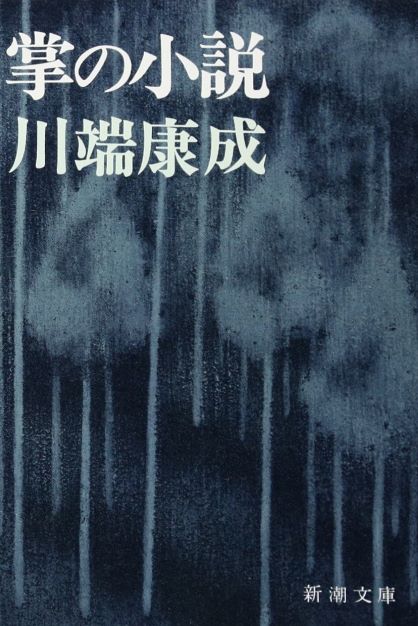
川端康成(かわばたやすなり)とは?
川端康成は、大正から昭和の戦前・戦後にかけて活躍した近現代日本文学の頂点に立つ作家の一人です。(1899~1972)
明治32(1899)年、大阪市北区で医師を務める川端栄吉の長男として誕生しました。幼い頃に両親を亡くし、母方の祖父母の手によって育てられます。成績も優秀であった川端は早くから作家を志します。
第一高等学校(旧制一高)から東京帝国大学国文学科(東京大学文学部)へと進み、創作活動を始めます。またこの頃、菊池寛に認められ、多くの作家の知己を得ます。

帝大卒業後は、新感覚派作家として独自の文学を貫き、流行作家へと階段を駆け上っていきます。やがてその文学性は国際的にも認められるようになり、昭和43(1968)年には、ノーベル文学賞を受賞しました。
そんな栄光溢れる川端の作家人生でしたが、思いがけない形で突如終わりを迎えます。昭和47(1972)年4月16日、逗子の仕事部屋でガス自殺をしてしまいます。なお、遺書はありませんでした。(享年・72歳)
著書には『伊豆の踊子』『雪国』『古都』『山の音』『眠れる美女』など、日本文学史に燦然と輝く名作が多数あり、その輝きは現代でも失われていません。
.jpg)
川端康成『伊豆の踊子』あらすじ【文豪もやっていた自分探し!】
川端康成『雨傘』『木の上』あらすじと解説【甘酸っぱい恋物語!】
川端康成『十七歳』あらすじと解説【イヤデスと言えない苦しみ!】
川端康成『日向』あらすじと解説【失った家族への憧れと希望!】
掌編小説『ざくろ』について
掌編小説『ざくろ』は昭和18(1943)年5月、文芸雑誌『新潮』に掲載されます。
「掌の小説」(たなごころのしょうせつ)について
※(てのひらのしょうせつ)とルビが付されている場合もあります。
川端康成は戦前戦後を通して一連の短い作品を書いています。その総数は128編ほどになるといわれ、これらも作品群を川端は「掌の小説」と名付けています。つまり掌に書きつけた小説とか、掌に入ってしまうささやかな小説ともうけとられます。
初期の頃の35編は大正15(1926)年6月15日に金星堂より刊行の処女作品集『感情装飾』に初収録されます。その後の昭和5(1930)年4月7日に新潮社より刊行の『僕の標本室』には、新作を加えた47編が収録され、昭和13(1938)年7月19日に改造社より刊行の『川端康成選集第1巻』には77編が収録されました。

改造社版『川端康成選集』第一巻のあとがきで作者自らこのように言っています。
私の旧作のうちで、最もなつかしく、最も愛し、今も尚最も多くの人に贈りたいと思ふのは、実にこれらの掌の小説である。この巻の作品の大半は二十代に書いた。多くの文学者が若い頃に詩を書くが、私は詩の代りに掌の小説を書いたのであつたらう。
無理にこしらえた作もあるけれどもまたおのづから流れ出たよい作も少なくない。今日から見るとこの巻を『僕の標本室』とするには不満はあつても若い日の詩精神はかなり生きてゐると思ふ。
けれども十二年後の全集で作者はこの評価をくつがえしています。
こんどこの全集のためにこれらの掌の小説を読みかへしてみて、 私は『最も愛し』てゐると言ふことはためらはれ、『若い日の詩精神はかなり生きてゐる』と言ふことにも疑ひを持つた。
と、川端康成は言うものの、作家の手を離れ読者のものとなった作品は、今でも一人一人の心に寄り添い続けています。
『ざくろ』あらすじ(ネタバレ注意!)

一夜の木枯らしに “ ざくろ ” の葉は散りつくしていました。雨戸を開けた「きみ子」はそんな光景に驚きます。梢にはみごとな果実がありました。「きみ子」は母を呼んでそのことを教えますが、母は、「忘れていた。」と、ちょっと見ただけで台所へ戻って行きました。
「きみ子」も母も、 “ ざくろの実 ” のことなど忘れて暮らしています。半月ばかり前、いとこの子供が遊びに来たとき、 “ ざくろ ” を見つけて木に登りましたが、そのときまでこの家では “ ざくろの実 ” を忘れていました。それからまた今朝まで忘れていたのです。
「きみ子」は庭に出て竹竿で “ ざくろの実 ” を取りました。その実は熟し切っていて、割れ目から覗いた粒々は日に光り、透き通っています。「きみ子」は “ ざくろ ” にすまなかったように思いました。

二階で縫物をしていると、十時頃、啓吉の声が聞こえました。母が、「きみ子、啓ちゃんが来たよ。」と大声で呼びます。「きみ子」はあわてて針山に針を刺しました。「きみ子もね、啓ちゃんが出征する前に、一度会いたいって言ってたんだけど……。」と母が言います。
※出征(しゅっせい) 戦争に行くこと。出戦。
母は、昼飯でもと引き止めますが、啓吉は急ぐ様子でした。そんな啓吉に母は、「うちのざくろ、おあがり。」と言って、また「きみ子」を呼びました。二階からおりて来た「きみ子」を、啓吉は待ち切れないような眼で迎えます。
そして啓吉の眼にふとあたたかいものが浮かびかかった時、「あっ。」と啓吉は “ ざくろ ” を落としてしまいました。二人は顔を見合わせて微笑します。「きみ子」の頬が熱くなりました。
「きみちゃんも、体に気をつけてね。」
「啓吉さんこそ……。」

啓吉が出て行ってからも「きみ子」は、庭の木戸の方を見送っていました。母は、啓吉が落とした “ ざくろ ” を台所で洗って来て「きみ子」に差し出します。「きみ子」は、「いやよ、きたない。」と、顔をしかめますが、頬がぱっと熱くなると、まごつきながらも素直に受け取りました。
啓吉が少し齧った “ ざくろ ” に「きみ子」は歯をあてます。 “ ざくろ ” の酸味とともに、悲しいよろこびを「きみ子」は感じました。そんな「きみ子」に母は一向無頓着で、立ち上がって鏡台の前を通ると、「おやおや、大変な頭。」と言って、そこに座ります。
そして母は、「お父さんが亡くなった当座はねえ。髪を梳くのが、こわくって……。お父さんが梳き終わるのを待ってらっしゃるような気がして、はっとしたりすることがあってね。」と言いました。

母がよく父の残しものを食べていたことを「きみ子」は思い出します。母はただ勿体ないと思っただけで、“ ざくろ ” をくれたのでしょう。「きみ子」は、秘密のよろこびに触れた自分が恥ずかしくなりました。
けれども、啓吉に知られないで、心いっぱいの別れ方をしたように思い、いつまでも啓吉を待っていられそうに思いました。母の方を見ると鏡台を隔てる障子にも、日がさしていました。
「きみ子」はもう、膝に持った “ ざくろ ” に歯をあてることも恐ろしいように思いました。
『ざくろ』【解説と個人的な解釈】
昭和初期の戦時中が物語の舞台です。「木枯らし」が吹いていることから季節は晩秋か初冬と言えるでしょう。主人公の「きみ子」は母親と二人で暮らしています。しかし戦時下という状況からか、二人は “ ざくろの実 ” のことを忘れています。
後ほど明らかになりますが、忘れている理由の一つとして「父親の逝去」も上げられます。そんな母と娘の元に啓吉が訪ねて来ます。「出征」の挨拶をするためですが、母が「啓ちゃん」と親しげに呼んでいることから「きみ子」と啓吉の関係は幼馴染と推測できます。
そして幼馴染の二人の視線が交差し、啓吉の眼から涙が溢れた瞬間、啓吉は “ ざくろ ” を落としてしまいます。啓吉の愛の視線を感じ取ったのでしょうか、「きみ子」は自分の恋心を意識します。
啓吉が去った後、母親から “ ざくろ ” を渡された「きみ子」は、啓吉が口をつけたものを自分が食べるという「秘密の悲しいよろこび」を味わいます。つまり「間接的な接触」を通して、啓吉と結ばれたかのように実感したのでしょう。
しかしそんな結びつきも、「啓吉の出征」という悲しい現実によって引き裂かれます。物語の最後の方では、「母は父の残しものを食べていた」といった「きみ子」の回想とともに、母の亡き夫に対する悲しみも語られます。
結末に語られる「 “ ざくろ ” を食べることが恐ろしいように思う」という場面についてですが、母の残しものを食べるという行為を「きみ子」は、「夫婦間の情愛」のように受け取ったと考えられます。
そして母にとって父が思い出の人になったと考えた「きみ子」は、啓吉も同様に思い出の人になるのではないか?との考えが頭を過り、恐ろしくなったと個人的に解釈しています。
あとがき【『ざくろ』の感想を交えて】
.jpg)
“ ざくろ ” の花言葉は「円熟した優雅さ」「子孫の守護」です。そして “ ざくろの実 ”は「愚かしさ」「結合」という花言葉を持っています。
川端康成の『ざくろ』を読むと、どうしてもこの花言葉のことを考えてしまいます。もしかしたら「きみ子」は、啓吉の齧った “ ざくろの実 ” を食べたとき「結合」と「子孫の守護」を思ったのではないかな?と。
文庫本で4ページ足らずの短い作品ですが、このように深読みしてしまう作品です。その後、二人がどのような人生を歩んだか分かりませんが、啓吉が無事に復員し、「きみ子」と一生添い遂げたと個人的に思いたいです。




コメント