はじめに【「癖」について】
誰にでも「癖」というものがあると思います。例え自分で気づいていなくても他人から指摘されて「はっ!」とするようなことも・・・。そんな自分の「癖」をコンプレックスと感じている人も多いでしょう。
「癖」というものは、人が無意識のうちに行ってしまう習慣的な行動のことです。「癖」を治す方法として、「習慣を変えたら良い」と言われていますが、口で言うほど簡単なことではありません。
ともかくとして、今回はそんな「癖」について思い悩む青年を主人公とした川端康成の掌編小説『日向』をご紹介したいと思います。
川端康成『日向』あらすじと解説【失った家族への憧れと希望!】
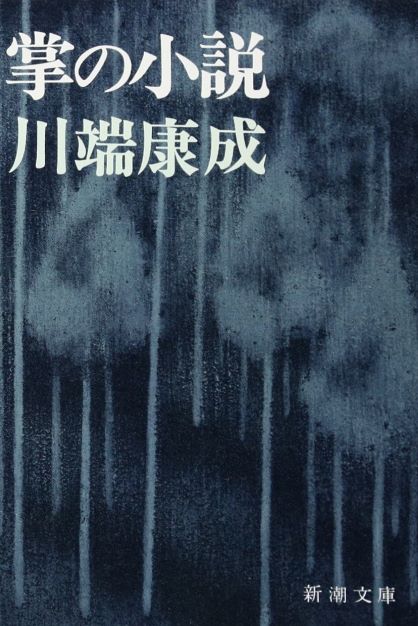
川端康成(かわばたやすなり)とは?
川端康成は、大正から昭和の戦前・戦後にかけて活躍した近現代日本文学の頂点に立つ作家の一人です。(1899~1972)
明治32(1899)年、大阪市北区で医師を務める川端栄吉の長男として誕生しました。幼い頃に両親を亡くし、母方の祖父母の手によって育てられます。成績も優秀であった川端は早くから作家を志します。
第一高等学校(旧制一高)から東京帝国大学国文学科(東京大学文学部)へと進み、創作活動を始めます。またこの頃、菊池寛に認められ、多くの作家の知己を得ます。

帝大卒業後は、新感覚派作家として独自の文学を貫き、流行作家へと階段を駆け上っていきます。やがてその文学性は国際的にも認められるようになり、昭和43(1968)年には、ノーベル文学賞を受賞しました。
そんな栄光溢れる川端の作家人生でしたが、思いがけない形で突如終わりを迎えます。昭和47(1972)年4月16日、逗子の仕事部屋でガス自殺をしてしまいます。なお、遺書はありませんでした。(享年・72歳)
著書には『伊豆の踊子』『雪国』『古都』『山の音』『眠れる美女』など、日本文学史に燦然と輝く名作が多数あり、その輝きは現代でも失われていません。
.jpg)
川端康成『伊豆の踊子』あらすじ【文豪もやっていた自分探し!】
川端康成『雨傘』『木の上』あらすじと解説【甘酸っぱい恋物語!】
川端康成『十七歳』あらすじと解説【イヤデスと言えない苦しみ!】
川端康成『ざくろ』あらすじと解説【きみ子の秘密の喜び!】
掌編小説『日向』(ひなた)について
『日向』は大正12(1923)年11月、『文藝春秋』に発表されます。
「掌の小説」(たなごころのしょうせつ)について
※(てのひらのしょうせつ)とルビが付されている場合もあります。
川端康成は戦前戦後を通して一連の短い作品を書いています。その総数は128編ほどになるといわれ、これらも作品群を川端は「掌の小説」と名付けています。つまり掌に書きつけた小説とか、掌に入ってしまうささやかな小説ともうけとられます。
初期の頃の35編は大正15(1926)年6月15日に金星堂より刊行の処女作品集『感情装飾』に初収録されます。その後の昭和5(1930)年4月7日に新潮社より刊行の『僕の標本室』には、新作を加えた47編が収録され、昭和13(1938)年7月19日に改造社より刊行の『川端康成選集第1巻』には77編が収録されました。

改造社版『川端康成選集』第一巻のあとがきで作者自らこのように言っています。
私の旧作のうちで、最もなつかしく、最も愛し、今も尚最も多くの人に贈りたいと思ふのは、実にこれらの掌の小説である。この巻の作品の大半は二十代に書いた。多くの文学者が若い頃に詩を書くが、私は詩の代りに掌の小説を書いたのであつたらう。
無理にこしらえた作もあるけれどもまたおのづから流れ出たよい作も少なくない。今日から見るとこの巻を『僕の標本室』とするには不満はあつても若い日の詩精神はかなり生きてゐると思ふ。
けれども十二年後の全集で作者はこの評価をくつがえしています。
こんどこの全集のためにこれらの掌の小説を読みかへしてみて、 私は『最も愛し』てゐると言ふことはためらはれ、『若い日の詩精神はかなり生きてゐる』と言ふことにも疑ひを持つた。
と、川端康成は言うものの、作家の手を離れ読者のものとなった作品は、今でも一人一人の心に寄り添い続けています。
『日向』あらすじ(ネタバレ注意!)

二十四歳の秋、主人公の「私」は、ある娘と海辺の宿で会います。それは恋の始めでした。そのとき娘は突然顔を隠しました。「私」は、(また悪い癖を出していたんだな……)と気がつきます。
「私」には、傍にいる人の顔をじろじろ見てしまう癖があります。直そうと思っていますが、身近な人の顔を見ないでいると苦痛になってしまいます。けれども “ この癖 ” を出している自分に激しい自己嫌悪を感じていました。
それは幼い頃に両親を失い、他家に厄介になっていたときに、(人の顔色ばかり読んでいたせいで、こうなったのではないか?)と思うからです。いつから “ この癖 ” が出来たのか懸命に考えたこともありましたが、明らかにしてくれるような記憶は浮かんで来ませんでした。

「私」は娘を見ないようにと、海の砂浜に眼を向けます。そこには秋の日光に染まった日向がありました。―――この日向が、「私」の埋もれていた古い記憶を呼び出して来ます。
※日向(ひなた) 日光(太陽光)が当たっている場所。または日光が当たる方向。日陰の反対語。
両親が亡くなってから「私」は、祖父と二人きりで十年近く田舎の家で暮らしていました。祖父は盲目で、何年も同じ部屋で長火鉢を前にして、東を向いて座っていました。そして時々首を動かして南を向き、決して顔を北に向けようとはしませんでした。
ある日祖父の “ その癖 ” に気がついた「私」は、祖父の前に座って、じっとその顔を見ていました。けれども祖父は五分毎に顔を南に向けるだけでした。南は日向です。南だけが盲目でも微かに明るく感じられるのだと「私」は思っていました。

―――忘れていた日向のことを「私」は、今思い出したのです。
相手が盲目だったから自然と祖父の顔を見ていることが多く、それが人の顔を見る癖になったのだと、この記憶で分かりました。
“ この癖 ” は、「私」の卑しい心の名残りではなかったのです。
「少し恥ずかしいわ。」娘が言いました。明るい顔で「私」は再び娘を見ます。娘は少し赤くなってから狡そうな眼をしてこう言いました。
「私の顔なんか、今に毎日毎晩で珍しくなくなるんですから、安心ね。」
―以下原文通り―
「私」は娘に親しみが急に加わったような気がした。娘と祖父の記憶とを連れて、砂浜の日向へ出てみたくなった。
『日向』【創作の背景】

川端は、本郷のカフェ「エラン」で女給をしていた14歳の伊藤初代に恋をし、足繁く通うようになります。しかし「エラン」は閉店することになり、初代は女主人の紹介で岐阜の寺に預けられることになります。川端は友人を伴い、岐阜の初代を訪ねます。
そして長良川岸の宿「みなと館」(現・ホテルパーク)で会って求婚します。その後川端は、初代の父の承諾を得るために、東大の友人3名を引き連れて、当時初代の父が働いていた岩手県の小学校を訪ね、承諾を得て婚約の運びとなります。
川端自身、『日向』について「海辺の宿は実は岐阜の長良川岸の宿である。しかし事実の通りではない」と話していることから、登場人物の「娘」とは伊藤初代のことと想像できます。
しかし婚約成立から1ヶ月後、突如初代から川端に婚約破棄の手紙が届き、二人は結ばれることなく別れることになります。ちなみに川端康成は、婚約者だった伊藤初代との関係を素材とした掌の小説を11編書いています。
『日向』【解説と個人的な解釈】

冒頭の「恋の始め」という部分、そして「宿で会っている」という事からも、二人の関係性は「付き合って間もない恋人同士」と見ることができるでしょう。更に最後の方で娘が口にする「毎日毎晩」という言葉から見ても「結婚が約束されている」と考えられます。
主人公の「私」には、「人の顔をじっと見てしまう癖」があります。「私」はその癖が、両親を亡くし、幼い頃から他家の世話になっていたせいで、人の顔色ばかり窺うようになったという「卑しい気持ちの表れ」ではないか?と思い悩んでいます。
娘の顔をじっと見ていたことに気づいた「私」は、海岸の砂浜に眼を向けます。そこには日向がありました。日向を見たことで古い記憶を思い出した「私」は、「盲目の祖父」の顔をいつも見ていたからだと “ 癖 ” の理由を導き出します。
物語の結末は、「娘と祖父の記憶とを連れて、砂浜の日向へ出てみたくなった。」と結ばれていますが、この部分に、作者・川端康成が幼き日に失った「家族」への憧れと希望が込められていると解釈しています。
あとがき【『日向』の感想を交えて】

実際に川端の祖父・三八郎は白内障を患っていて盲目でした。その祖父が他界し、肉親の全てを喪ったのは川端が満14歳のときです。言うなれば他人に育てられる訳ですから人の顔色を窺ってしまうのは当然のことです。
そんな自分の卑しい心持ちに自己嫌悪を抱くのも分かります。けれども「癖」の理由が卑しさからではないと分かったとき、それは一瞬で暗闇から抜け出たような気持ちだったでしょう。恋する女性の存在も大きかったと思われます。
『日向』の主人公の「癖」は、彼の人生そのものと言えます。決して恥ずべき「癖」ではなかったのです。とても短い小説ですが、亡き祖父への感情、そして娘との「恋の始まり」が色濃く描かれていて、タイトル同様に温かい気持ちにさせてくれる作品です。
現実の恋も成就したら良かったのですが、人生は思い通りにいかないってことですか・・・。




コメント