はじめに【罪責感(ざいせきかん)について】
「罪責感」という言葉があります。一般的に重大な過失を犯したという理由で、「誰それに対して申し訳ない」と、自分を責めたり苛む意識や感情のことで、「罪悪感」よりも罪の意識が強いときに使われます。
このような「罪責感」を抱えながら必死で生きている人間が、ことのほか多いと想像します。かくいうわたしもそんな人間の一人です。とは言え、過失にも、意図的に起こした過失と、偶発的に起こしてしまった過失の二種類があります。
いずれも「罪責感」に苛まれるという点では同じですが、後者の場合は同時に、自らの運命を呪うしかなくなるでしょう。数奇的なめぐり合わせと言うべきか、この世の中には説明の出来ない不可思議なことが起こりうるものです。
山川方夫『夏の葬列』あらすじと解説【付きまとう罪責感の呪縛!】

山川方夫(やまかわまさお)とは?
山川方夫(本名:山川嘉巳)は日本の小説家です。(1930-1965)
山川は東京市下谷区上野桜木町(現在の東京都台東区上野桜木町)に、日本画家・山川秀峰の長男として生まれます。
昭和27(1952)年、慶應義塾大学文学部仏文科を卒業し、同大学の大学院に進みます。この頃『三田文学』に参加します。その後大学院は中退しますが『三田文学』の活動を通して、新人発掘に力を注ぎ、江藤淳、曽野綾子らを世に出す傍ら、自らも同誌に『日々の死』を連載します。
※『三田文学』 永井荷風を中心に森鴎外、上田敏を顧問として創刊された慶応義塾大学文学部の機関誌(文芸雑誌)。

永井荷風『にぎり飯』【めぐり逢いは絶望を過去へと押し流す!】
昭和33(1958)年、『演技の果て』で第39回芥川賞候補となり、翌昭和34(1959)年にも『その一年』『海の告発』が第40回芥川賞候補となります。その後も芥川賞や直木賞の候補となりますが、ついに受賞が叶うことはありませんでした。
『夏の葬列』などを収録した掌編集『親しい友人たち』や『長くて短い一年』を刊行し、その一編は翻訳され海外にも紹介されますが、昭和40(1965)年2月19日、交通事故で死去してしまいます。(没年齢:34歳)
他に代表作として『お守り』『海岸公園』『クリスマスの贈物』『愛のごとく』等があります。

短編(掌編)小説『夏の葬列』について
『夏の葬列』は昭和37(1962)年、『ヒッチコックマガジン』(宝石社から1959年から1963まで発行)8月号に掲載され、翌昭和38(1963)年4月、短編集『親しい友人たち』に収録されます。
『夏の葬列』あらすじ(ネタバレ注意!)

海岸の小さな町の駅に下りて、「彼」は、しばらくあたりを眺めていました。駅前の風景はすっかりと変わっています。「彼」は戦争の末期、疎開児童としてこの町に三か月ほど住んでいました。
そんな「彼」も、今は大学を出て就職をし、一人前の出張帰りのサラリーマンとしてこの町に来ています。夏の真昼でした。時間に余裕のあった「彼」は、町を散策することにします。
ところが、見覚えのある一本の松が植えられた丘にさしかかったとき、「彼」は、化石にでもなったかのように足を止めてしまいました。青々とした芋畑の向こうに、喪服を着た小さな葬列が動いていたのです。
―――「彼」は一瞬、十数年前のある風景に再び自分が舞い戻ったかのような錯覚に陥ります。

「彼」は、真白なワンピースを着た、同じ疎開児童のヒロ子さんと並んで、小さな葬列を眺めていました。ヒロ子さんは二歳年上の五年生で、弱虫の「彼」をいつもかばって、そばにいてくれました。
ヒロ子さんは「彼」に「お葬式だわ。」と言い、「お葬式に子供が行くとお饅頭をくれるの。」と、教えてくれます。「彼」は唾をのみこみ「競争だよ!」と叫んで、駆け出しました。「彼」は、芋畑の中を夢中で駆け続けます。
するとそのときでした。凄まじい爆音と炸裂音が響き渡り、「カンサイキだあ!」と誰かが叫びます。(艦載機だ)―――「彼」は恐怖のあまり芋畑の中に倒れこみます。別の男が「その女の子、走っちゃだめ!白い服はぜっこうの目標になるんだ!」と、叫びました。

「彼」は思います。(白い服――きっとヒロ子さんだ。ヒロ子さんは撃たれて死んじゃうんだ。)「彼」は畑の土に頬を押し付け、けんめいに呼吸を殺していました。すると突然、視野に白いものが入ってきて「彼」を抑えつけます。
「早く逃げるの。早く!」顔を真っ青にしたヒロ子さんが「彼」に言います。「彼」は思います。(ヒロ子さんといっしょに殺されちゃう。)その途端、「彼」は狂ったような声で「向うへ行け!目立っちゃうじゃないかよ!」と叫びます。
そして「彼」は、「……むこうへ行け!」と、全身の力でヒロ子さん突き飛ばしたのです。そのとき強烈な衝撃が地べたを叩きます。「彼」は、仰向けに突きとばされたヒロ子さんが、まるでゴムマリのようにはずんで空中に浮くのを見たのでした。
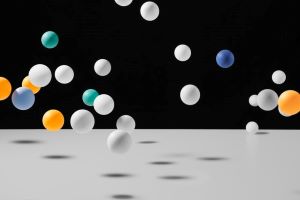
葬列は、あまりにも記憶の中のあの日の光景に似ていたのです。「彼」は、自分には夏以外の季節がなかったような気がしていました。殺人をおかした、戦時中の、あのただ一つの夏の季節だけが、自分を取り巻き続けているような気がしていたのです。
ヒロ子さんは重傷でした。けれども「彼」は、ヒロ子さんのその後を聞かずにこの町を去ったのです。翌日に戦争が終わったからでした。葬列は「彼」のほうに向かってきます。そのとき「彼」の目は、柩の上に置かれた写真を捉えます。
その写真には、ありありと昔のヒロ子さんの面影が残っていました。三十歳近くなったヒロ子さんの写真だったのです。―――(おれは、人殺しではなかったのだ)「彼」は胸に湧き上がるものを、けんめいにおさえつけながら思います。

「彼」は葬列のあとに続く子供たちの一人に「何の病気で死んだの?この人。」と、訊ねました。するとその子供は「川に飛び込んで自殺しちゃったのさ。」と答えます。続けて「彼」は、「へえ、失恋でもしたの?」と聞きました。
子供はおかしそうに笑いながら「バカだなあ。この小母さん、もうお婆さんだったんだよ。」と言います。「彼」は「お婆さん?あの写真だったら三十くらいじゃないか。」と疑問を口にすると、別の子供がこのように語ったのでした。
「昔の写真しかなかったんだって。あの小母さん戦争で、一人きりの女の子がこの畑で機銃で撃たれて死んじゃってね。それからずっと気が違っちゃってたんだもん。」

「彼」は、葬列のあとを追いませんでした。追う必要がなかったのです。(この二つの死は結局、俺のなかに埋葬されるほかはないのだ)と、思います。そして(敗戦の夏のあの記憶を追放し、自分の身を軽くするだけのためにこの町に下りてみたのに)と、心の中で本音を漏らします。
―――(なんという偶然の皮肉だろう)
やがて「彼」は、駅の方向に向けて歩き出しました。そして(俺はきっと自分の夏のいくつかの瞬間を、一つの痛みとしてよみがえらすのだろう……)と、思います。(もはや逃げ場所はないのだ……)という意識が「彼」の足どりをひどく確実なものにしていたのでした。
青空文庫 『夏の葬列』 山川方夫
https://www.aozora.gr.jp/cards/001801/files/59532_70200.html
『夏の葬列』【解説と個人的な解釈】
昭和20(1945)年8月15日、日本政府は、昭和天皇による玉音放送をもって俗に言う「太平洋戦争」を終結させます。物語の舞台設定はこの前日、8月14日になっています。
主人公の「彼」は、十数年前に犯した “ 罪 ” の罪責感を抱えて生きています。そんな「彼」が再び因縁の町に足を踏み入れるというのは余程のことです。物語の後半部で語られますが、それは「自分の身を軽くするだけのため」でした。
ですから偶然にも、当時と同じような風景を目の当たりにし、それが被害者のヒロ子さんの葬列だと解釈した「彼」は、心の中で喜び、一時ですが、罪責感からも解放されます。そこにはかつての友人の死を悼む気持ちなど存在していません。
そんな「彼」の心情に鉄槌を下すが如く、「彼」にとって最も残酷な事実を告げられます。つまり、自分ひとりの救済を望んでこの町にやって来た「彼」ですが、救済どころか、二重の罪責感を背負うことになるのです。
そして「彼」は、夏の到来ごとに伴うであろう “ 痛み ” を覚悟し、「もはや逃げ場所はないのだ。」との思いに至りながら、因縁の町を後にするのです。
あとがき【『夏の葬列』の感想を交えて】

『夏の葬列』という作品は、人間のエゴイズムについて良く語られます。確かに極限状態に置かれたとき、人間は、非情かつ残酷な動物の本能を見せます。わたし自身、主人公の「彼」と同じ状況に置かれたら同じ行動を取るかも知れません。誰も我が身が一番可愛いのですから。
けれども、そんな人間の残酷さよりも、一人の少年をそのような極限状態に置かざるを得なくした “ 戦争 ” という愚行を断罪するべきでしょう。被害者であるはずの幼い子供が加害者になってしまうという残酷な物語ですが、そもそも “ 戦争 ” がなかったらこのような悲劇は起きませんでした。
『夏の葬列』はあくまでフィクションです。けれども当時は、似たような経験をした人間が多かったことでしょう。そして「罪責感」を抱えながら必死で生き続けていたことでしょう。いや、今もこの世界では同じような悲劇が起こり続けています。
「歴史は繰り返す」と、古代ローマの歴史家クルティウス・ルフスが言いましたが、人間は歴史から何も学んでいないようです。




コメント