はじめに【8050問題について】
かつて “ 引きこもり問題 ” といえば少年少女の問題でした。しかし、現在は『8050問題』といった中高年の引きこもりが社会問題になっています。
内閣府が発表した「平成30年度調査」によると、40~64歳のひきこもりが全国に61万3000人いると推計されています。最近では『8050問題』を背景とした悲惨な事件も珍しくはありません。
詳しく知りたい方は報告書をご覧になって下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000525388.pdf
では、このような問題は「自己責任」なのでしょうか。決してそうとは言えないでしょう。社会や政治が作り出した社会問題なのです。理由のひとつとして景気の低迷期が長く続いていることが挙げられます。
本来なら支援しなければならない人達を社会は犠牲にし、そして、見放してきたのです。こんなニュースが流れるとき、わたしは決まって、とある小説を思い出します。
井伏鱒二『山椒魚』あらすじと解説【窮地に陥った者の悲鳴!】
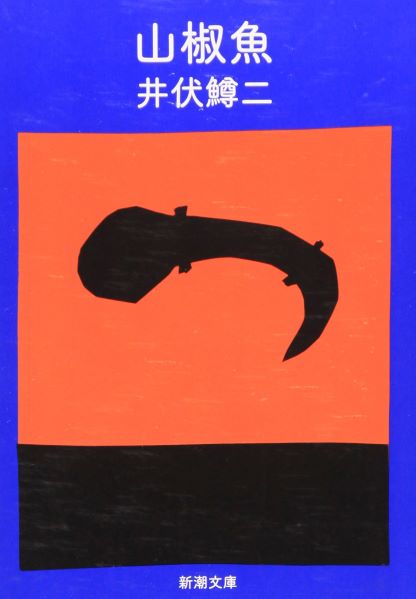
井伏鱒二(いぶせますじ)とは?
井伏鱒二(本名・満寿二)は昭和から平成にかけて活躍した日本の小説家です。
広島県深安郡加茂村(現・福山市)に、地主の次男として生まれます。(1898~1993)学生時代は、早稲田大学英文科や日本美術学校に在籍しますが、どちらも中退をしてしまいます。
のちに、長い同人誌習作時代を経て、昭和4(1929)年、『山椒魚』や『屋根の上のサワン』その他の先品で文壇に認められます。昭和13(1938)年、『ジョン萬次郎漂流記』で第6回直木賞を受賞します。
面倒見のよい人柄で知られ、多くの弟子を持ちます。特に太宰治には目をかけ、昭和14(1939)年、山梨県甲府市出身の地質学者・石原初太郎の四女の石原美知子を太宰に紹介し、結婚を仲介しています。
その作風は、広島における原爆被災の悲劇を日常生活の場で淡々と描いた『黒い雨』で、高みに達します。作品として他に、『本日休診』『漂民宇三郎』『荻窪風土記』などがあります。平成5(1993)年6月24日、東京衛生病院に緊急入院し、7月10日に肺炎のため95歳で死去します。
.jpg)
井伏鱒二『太宰治のこと』要約【桜桃忌に読みたい作品④!】
井伏鱒二『屋根の上のサワン』あらすじと解説【手放すことも愛!】
井伏鱒二『へんろう宿』あらすじと解説【「お接待」慈悲の心!】
小説『山椒魚』(さんしょううお)について
『山椒魚』は、井伏鱒二の代表作ともいえる短編小説です。井伏の学生時代の作品『幽閉』を改稿したもので、昭和4(1923)年、同人雑誌『文芸都市』5月号に掲載され、その後作品集『夜ふけと梅の花』に収録されます。
このように、大学上京後から太宰は井伏に師事し、結婚の仲人も井伏に務めてもらいます。戦後になると、太宰は井伏に複雑な感情を抱いていたようで、遺書に「井伏さんは悪人です」と書き残していたことは広く知られています。しかし、両者の確執には様々な説があり、詳しくは分かっていません。
『山椒魚』あらすじ(ネタバレ注意!)

山椒魚は悲しんでいます。岩屋をねぐらにしていたのですが、あるとき、自分が岩屋の外に出られなくなっていたことに、気が付いたからです。それは彼の体が二年の間に大きく成長したからでした。
出て行こうとも試みたのですが、頭が出入り口を塞ぐ「コロップの栓」(コルクの栓)のようになってしまいます。そのことは彼を狼狽させ、悲しませるには十分でした。狭い岩屋の中ですから、自由に歩き回ることもできません。
「いよいよ出られないというならば、俺にも相当な考えがあるんだ。」
彼はそう言って息巻いているのですが、何一つとして良い考えは浮かびません。
彼は岩屋の入り口から外の谷川を眺めことを好んでいました。
谷川ではメダカの群れが、流れに押し流されまいと必死です。群れは先頭の動きに合わせ、右に左にとよろめいていました。山椒魚はその様子を見て「不自由千万なやつらだ!」と嘲笑します。渦に巻き込まれて沈んでいく白い花弁に「目がくらみそうだ」と呟きます。
※嘲笑(ちょうしょう) あざけって笑いものにすること。

ある夜のことでした。岩屋の中に一匹の小海老が紛れ込みます。小海老は山椒魚の横っ腹にしがみついて、卵を産みつけているようです。多分ですが、山椒魚の横っ腹を岩石とでの勘違いしているのでしょう。そうでもければ物思いにでもふけっているのかもしれません。
山椒魚は得意げに言います。
「屈託したり物思いにふけったりするやつは、ばかだよ。」
そして彼は(どうしても岩屋の外に出なくてはならない)と決心します。
彼は全身の力をこめて岩屋の出口に突進しました。しかし前回と結果は同じです。またもや「コロップの栓」のようになり、再び力一杯、後ろに身を引かなければならなくなりました。横っ腹にしがみついていた小海老は狼狽します。

しかし、自分が岩石だと信じていた物が、「コロップの栓」のようになったり抜けたりしている光景を目の当たりにして、その狼狽は失笑へと変わるのでした。その後、山椒魚は外に出ようと再び同じことを試みますが、それは徒労に終わっていまいます。
※徒労(とろう) むだな骨折り。
彼は目から涙を流します。そして神に向かって「たった二年間うっかりしていただけなのに、その罰として、一生涯、穴蔵に私を閉じ込めてしまうとは横暴です。」と、窮状を訴えます。その姿はまるで、牢屋に囚われている囚人のようでした。
※窮状(きゅうじょう) 困り果てている状態。
岩屋の外では、水すましや蛙が自由気ままに動き回っています。最初はその様子を感動的な瞳で眺めていた山椒魚でしたが、やがて、そうしたものからはむしろ目をそむけたほうが良いと考えます。そして瞳を閉じたまま、開こうとはしませんでした。

彼は自分が唯一自由にできる暗闇の世界に没頭します。そして「ああ、寒いほど独りぼっちだ!」と言い、思わずすすり泣いてしまいました。そうしているうちに彼は、悪い性質を帯びてきます。
ある日、岩屋に飛び込んできた蛙を閉じ込めて、外に出られないようにしました。蛙は驚いて岩壁をよじ登り、安全な場所へとその身を隠します。この蛙は前に山椒魚が羨ましそうに眺めていた、あの蛙でした。

山椒魚は「一生涯ここに閉じ込めてやる!」と言います。蛙は「俺は平気だ。」と言い返します。そして彼らは激しい口論を始めます。このような喧嘩を繰り返しながら、月日は、一年、二年と過ぎていきました。
そんなある夏のことでした。山椒魚と蛙は黙り込んでいます。それはお互いに自分の嘆息を相手に聞かせまいと注意をしながら過ごしているからでした。そんな中、蛙は不注意にも「ああああ」とった小さな嘆息を漏らしてしまいます。
※嘆息(たんそく) なげいて、ため息をつくこと。非常になげくこと。
その嘆息は山椒魚にも届いていまいました。そして蛙に「もう、そこから降りてきてもよろしい。」と言います。けれども、蛙は「空腹で動けない。」と答えます。そして、そんな蛙に山椒魚は「おまえは今、どういうことを考えているのだろうか?」と聞きます。
蛙は遠慮がちに答えます。
「今でも別におまえのことを怒ってはいないんだ。」
太宰治の『山椒魚』評
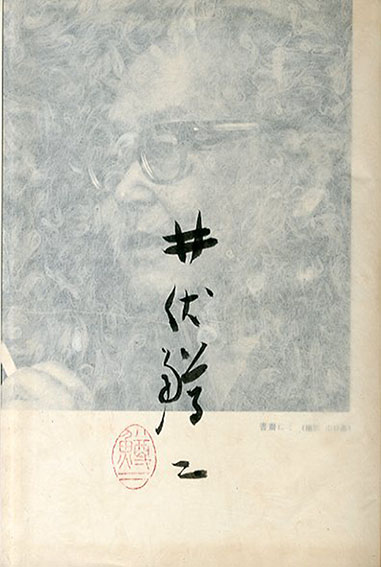
私は十四のとしから、井伏さんの作品を愛読していたのである。二十五年前、あれは大震災のとしではなかったかしら、井伏さんは或るささやかな同人雑誌に、はじめてその作品を発表なさって、当時、北の端の青森の中学一年生だった私は、それを読んで、坐っておられなかったくらいに興奮した。それは、「山椒魚」という作品であった。
童話だと思って読んだのではない。当時すでに私は、かなりの小説通を以てひそかに自任していたのである。そうして、「山椒魚」に接して、私は埋もれたる無名不遇の天才を発見したと思って興奮したのである。
『井伏鱒二選集』後記 太宰治
青空文庫 『井伏鱒二選集』後記 太宰治
https://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/42359_15871.html
井伏鱒二と太宰治の関係性
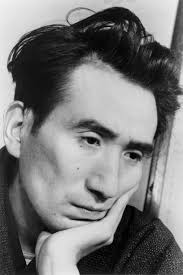
井伏鱒二と太宰治は師弟関係にあたります。先述したように、太宰がまだ青森の中学生だった頃、井伏の『幽閉』(『山椒魚』の原形)を読んでその才能に興奮します。そして高校生となった太宰は井伏に一通の手紙を出します。
私は二十五年間、井伏さんの作品を、信頼しつづけた。たしか私が高等学校にはいったとしの事であったと思うが、私はもはやたまりかねて、井伏さんに手紙をさし上げた。そうしてこれは実に苦笑ものであるが、私は井伏さんの作品から、その生活のあまりお楽でないように拝察せられたので、まことに少額の為替など封入した。
そうして井伏さんから、れいの律儀な文面の御返事をいただき、有頂天になり、東京の大学へはいるとすぐに、袴をはいて井伏さんのお宅に伺い、それからさまざま山ほど教えてもらい、生活の事までたくさんの御面倒をおかけして、そうしてただいま、その井伏さんの選集を編むことを筑摩書房から依頼されて、無量の思いも存するのである。
『井伏鱒二選集』後記 太宰治
太宰治『富嶽百景』【富士という御山になぜ人は魅せられるのか】
『山椒魚』【解説と個人的な解釈】
作者井伏鱒二は『山椒魚』について、次のように語っています。
サンショウウオを見たのは(旧制福山)中学の池で飼っていたのを見たのが始めてだが、(中略)川の中にいるサンショウウオは見たことがない。僕たちの家の通りの川にはいないから。(中略)まあ空想なんだ。
「井伏さんの録音テープ」(『井伏鱒二全集』第十八巻月報15)
また井伏は、次のような発言も残しています。
ぼくは、小説も随筆も詩も書くといわれているけど、小説だか随筆だかわからない作品があると訊かれたときは、ウソがあってもいいのが小説だと言うんだ。
『井伏鱒二聞き書き』萩原得司(潮出版社)

つまり井伏は、空想を用いて『山椒魚』を描いています。ですから、岩屋に閉じ込められ、そこから永遠に抜け出せなくなって窮地に置かれた “ 山椒魚の心理面 ” に焦点が置かれた作品と言えるでしょう。
当初は自分の不幸をただ悲しむだけの山椒魚でしたが、そのうち岩屋の入口から眺めた外の世界を嘲笑したり、紛れ込んだ小海老を馬鹿にするようになります。けれども自分が二度と岩屋から出られないことを悟ると、泣きながら神に窮状を訴えるようになります。
次に山椒魚は、外の世界から目を背けるようになり、一人の世界に没頭するようになります。そうこうしているうちに岩屋に飛び込んできた蛙を閉じ込めるといった悪さをします。外の世界を自由に動き回っていた蛙を自分と同じ境遇に追い込もうという訳です。
山椒魚と蛙は喧嘩を繰り返しながら月日は過ぎていきます。そんなある日、蛙の嘆息をきっかけに両者は歩み寄ります。そして山椒魚は、被害者と言える蛙の寛容さを知るところで物語は閉じられます。
窮地に置かれたとき、精神状態は目まぐるしく変化をします。ときには悪いことと知りながらも傷つけたりもします。もしかしたら井伏自身もそんなことがあったのかも知れません。そんな自らの意思でコントロールできない精神状態をユーモラスに描いた作品と考えます。
あとがき【『山椒魚』の感想を交えて】

その後の山椒魚と蛙はどうなったのだろうか。
始めてこの小説を読んだときから、わたしはいつもそんな空想を膨らませていました。
(以下、勝手に空想)
この谷川を長雨が襲います。水かさは増し、岩屋の中にはもう、蛙がしがみつく岩肌もありません。力尽きた蛙はもはや、水に体を任せるしかありませんでした。
そんな蛙を山椒魚はしかとその小さな両手で抱えます。そして彼は「ごめんな。ごめんな。」と言いながら大粒の涙を流すのでした。蛙は何も語ろうとはしません。しかしその顔は、いかにも満足そうです。
突如、大きな落雷の音が鳴り響くと同時に、激しい揺れがこの岩屋を襲います。
水の中は澱み、何も見えません。山椒魚は必死で蛙を庇います。蛙のまた、山椒魚にしがみついていました。
あくる朝、岩屋の中に眩しいくらいの朝日が差し込みます。山椒魚は閉じていた目をゆっくりと空けました。そして蛙を揺り起こして、こう言います。
「おい、岩屋の入り口が開かれてるぞ。」
物語の感想として逸脱しているかも知れませんが、つまりは想像力を膨らませてくれる作品と言えるでしょう。




コメント