はじめに【「中二病」という言葉について】
「中二病」という言葉があります。思春期に特徴的な、自分をよくみせるための背伸びや、自己顕示欲と劣等感が交錯する言動や態度を揶揄する言葉とされていますが、一説にはラジオ番組のコーナーから生まれた造語と言われています。
自分自身、思春期というものを振り返って見ると、毎日が葛藤と苦悩の連続でした。身の回りのこと、いや、世の中全てが気に食わず、だからといって何も出来ぬ自分の無力さに絶望したものです。
果たしてあの頃の自分は病気だったのかと問われると、それは違うと思っています。大人への階段を上るうえでの障害のようなものだったような気がします。ですから、つまずいたり転んだりするのは当たり前なのです。
太宰治『女生徒』あらすじと解説【幸福は一夜おくれて来る!!】

太宰治(だざいおさむ)とは?
昭和の戦前戦後にかけて、多くの作品を残した小説家です。本名・津島修治。(1909~1948)
太宰治は、明治42(1909)年6月19日、青森県金木村(現・五所川原市金木町)の大地主の家に生まれます。
青森中学、旧制弘前高等学校(現・弘前大学)を経て東京帝国大学仏文科に進みますが後に中退します。この頃、井伏鱒二に弟子入りをし、本格的な創作活動を始めました。しかし、在学中から非合法運動に関係したり、薬物中毒になったり、または心中事件を起こすなど、私的なトラブルは後を絶ちませんでした。
.jpg)
井伏鱒二『山椒魚』あらすじと解説【窮地に陥った者の悲鳴!】
井伏鱒二『太宰治のこと』要約【桜桃忌に読みたい作品④!】
井伏鱒二『屋根の上のサワン』あらすじと解説【手放すことも愛!】
井伏鱒二『へんろう宿』あらすじと解説【「お接待」慈悲の心!】
一方、創作のほうでは『逆行』が第一回芥川賞の次席となるなど、人気作家への階段を上り始めます。昭和14(1939)年、井伏鱒二の世話で石原美知子と結婚し、一時期は平穏な時間を過ごし『富嶽百景』『走れメロス』『駆込み訴へ』など多くの佳作を書きます。
戦後、『斜陽』で一躍、流行作家となりますが、遺作『人間失格』を残して、昭和23(1948)年6月13日、山崎富栄と玉川上水で入水自殺をします。(享年38歳)ちなみに、玉川上水で遺体が発見された6月 19日(誕生日でもある)を命日に、桜桃忌が営まれています。
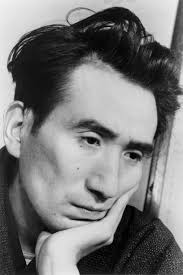
太宰治の故郷・青森県(津軽)にご関心のある方は下記のブログを参考にして下さい。
太宰治『津軽』要約と聖地巡礼!【序編―青森市・弘前市・大鰐町】
太宰治『津軽』要約と聖地巡礼!【本編①-外ヶ浜町・今別町】
太宰治『津軽』要約と聖地巡礼!【本編②-五所川原市・西海岸】
短編小説『女生徒』について
『女生徒』は、昭和14(1939)年刊行の『文學界』4月号に発表されます。7月に短編集『女生徒』(砂子屋書房)に収録されたのち、昭和17(1942)年6月、『女性』(博文館)に再収録されます。
太宰治の〈女性語り〉作品群の中で最も高い評価を得た作品とされていて、川端康成は「文芸時評」で、次のように評しています。
この女生徒は可憐で、甚だ魅力がある。少しは高貴でもあるだろう。(略)作者は「女生徒」にいわゆる「意識の流れ」風の手法を、程よい程度に用いている。それは心理的というよりは叙情的に音楽じみた効果をおさめている。
(「文芸時評」『文藝春秋』1939年5月 川端康成)
.jpg)
太宰治の女性独白体(女性語り)小説
・『燈籠』(1937) 父母と暮らす24歳の下駄屋の娘
・『女生徒』(1939) 父親を亡くしたため、母親と二人で暮らす女子学生
・『葉桜と魔笛』(1939) 20歳の頃を回想する55歳の夫人
・『皮膚と心』(1939) 28歳の妻
・『誰も知らぬ』(1940) 23歳の頃を回想する41歳の夫人
・『きりぎりす』(1940) 24歳の画家の妻
・『千代女』(1941) 18歳の少女
・『恥』(1942) 小説のモデルにされたと勘違いした女性の読者
・『十二月八日』(1942)一児の母でもある小説家の妻
・『待つ』(1942) 毎日駅で誰かを待つ20歳の女性
・『雪の夜の話』(1944) 小説家の妹で年齢は20歳くらい
・『貨幣』(1946) 百円紙幣の女性
・『ヴィヨンの妻』(1947) 詩人の妻で一児の母でもある26歳の女性
・『斜陽』(1947) 妻子ある小説家の愛人
・『おさん』(1947) ジャーナリストの妻で三児の母
・『饗応夫人』(1947) 饗応好きな女主人のもとで働く女中
『女生徒』あらすじ(ネタバレ注意!)

『女生徒』は、女性独白体(女性語り)で書かれています。
主人公の「私」は、(朝、眼をさますときの気持ちは面白い)と思っています。箱をあけると中に小さな箱があって、その小さな箱をあけると、もっと小さな箱が出てきて、それを繰り返していくと最後にサイコロくらいの小さい箱が出てきて、あけて見ても中身は空っぽ。あんな感じです。
朝は一番虚無です。寝床の中で、「私」はいつも厭世的です。朝は意地悪です。眼鏡はお化け。鏡台の前に座ると、眼鏡をかけている自分が嫌になります。そのせいか、目の美しいことが一番だと思います。鏡に向かうと(潤いのある目になりたい)と、つくづく思うのです。
※厭世的(えんせいてき) 人生に絶望し、世をはかなむ傾向にあるさま。
けさから五月、そう思うと少し浮き浮きしてきます。お父さんの死んだという事実が不思議に思われます。部屋の掃除を済ませ、昨日縫い上げた新しい下着を着ます。胸のところに、小さく白い薔薇の花を刺繍して置きました。「私」は少し得意気です。

ご飯をすまして、戸締りをしてから、門の前の草を少しむしって、お母さんへの勤労奉仕をします。同じ草でも、可愛い草と、そうでない草があります。理窟はなく、女の好き嫌いなんて、ずいぶんいい加減なものだと思います。
駅への道を急いでいる途中、四五人の労働者と一緒になります。その労働者たちは「私」に向かって、言えないような厭な言葉を吐きかけました。「私」は泣きそうになりながらも、その者たちに向かって笑ってやります。その口惜しさは電車に乗ってからも消えませんでした。
いつのも通り、吊り革にぶら下がって雑誌を読んでいるうちに、ひょんなことを思います。(自分は本に頼って生きている)。人のものを盗んで来て自分のものに作り直す才能は、そのずるさは、「私」の唯一の特技です。読む本がなくなって、真似するお手本が見つからなくなった時、どうすればいいのだろう。

雑誌には「若い女の欠点」という見出しで、色んな人が書いています。どこか自分のことを言われたような気がして恥ずかしい気にもなります。宗教家はすぐに信仰を持ち出すし、教育家は、恩、恩、とばかり書いています、政治家は漢詩を持ち出し、作家は気取って、おしゃれな言葉を使っています。
けれども、ここに書かれてある言葉全部が、なんだか、ただ書いてみたという感じがします。学校の修身と、世の中の掟と、すごく違っているのが、大きくなるにつれて分かってきました。嘘をつかない人なんて、あるかしら。あったらその人は、永遠に敗北者です。
※修身(しゅうしん) 修身教育。第2次大戦前,近代日本の小・中学校で修身科を中心として行われた道徳教育。
自分の個性を本当は愛しているのだけれども、それを体現するのはおっかないのです。人々が、良いと思う娘になろうといつも思います。けれども、気持ちと裏腹な行動をすると卑屈になります。早く道徳が一変するときが来れば良いと思います。そうすると、こんな卑屈さも無くなるでしょう。

席が空いて座ると、隣に厚化粧のおばさんがいて、ぶってやりたいほど厭でした。向かいの席には覇気のない四、五人のサラリーマンが座っています。けれども「私」が、このうちの誰か一人に笑いかけただけで、結婚する破目におちるかも知れません。女は自分の運命を決するのに、微笑一つでたくさんなのです。
二、三日前から庭の手入れに来ている植木屋さんの顔が目にちらついて仕方がありません。大袈裟に言うと、思索家みたいな顔をしています。植木屋さんにして置くには惜しい気がします。けさはほんとに、妙なことばかり考えます。御茶ノ水駅で下車したら、なんだかすべて、けろりとしていました。
※思索家(しさくか) 思索する人。物事の筋道をたてて深く考える人。
授業が始まります。けさの小杉先生は綺麗。山中、湖畔の古城に住んでいる令嬢、そんな感じがします。けれども、性格は難解で、お話しはいつも固く、愛国心について永々と説いて聞かせているのだけれども、(誰でも自分の生まれたところを愛する気持ちがあるのに)と、つまらなく思います。
ぼんやり窓の外を眺めていると、お庭の隅に、薔薇の花が四つ咲いていました。ぽかんと花を眺めながら、(人間も、本当によいところがある)と思います。花の美しさを見つけたのは人間だし、花を愛するのも人間だもの。

午後の図画の時間は、伊藤先生のモデルにさせられます。「私」の絵を画いて、こんど展覧会に出すそうです。けれどもモデルになりながら(こんな心の汚い私をモデルなんかにして、先生の画はきっと落選だ)と、思います。(先生は、私の下着に、薔薇の刺繍のあることさえ、知らないのですから……)
放課後は、お寺の娘のキン子さんと髪を切りに行きます。けれども頼んだようにできていなくてがっかりです。「私」はちっとも可愛くない。あさましい気がします。キン子さんは「お寺の娘はお寺に嫁入りするのが一番いい。一生食べるのに困らないし。」と言って「私」を驚かせます。
キン子さんは可愛い娘さんです。けれども時々いやになります。なんだか憂鬱です。バスの中で、胸がむかむかするような、いやな女の人を見て、朝に電車で隣になった厚化粧のおばさんを思い出します。ああ、汚い。女は厭だ。いっそこのまま少女のままで死にたくなります。
バスから降りて、田舎道を歩きます。途中、青草原に仰向けに寝転がり「お父さん」と呼んでみます。夕焼けの空は美しい。この空には、生まれてはじめて頭を下げたいのです。「私」は、いま神様を信じます。(みんなを愛したい)と涙が出そうなくらい思いました。美しく生きたいと思います。

帰宅すると、お客様がいました。客間のほうからお母さんたちの笑い声が聞こえてきます。「私」はなんだか、むかっとしました。お母さんは、お客が来ると、へんに冷たくよそよそしくなります。「私」はそんな時に、一ばんお父さんが懐かしく悲しくなります。
お客様の夕食の準備をしながら、小金井の家に住んでいた頃を思い出します。お姉さんはまだお嫁に行く前で、お父さんがいて、お母さんはまだ若く、「私」はただ、甘えていればよかったのです。気がつくと「私」はお鍋に両手をつっこんだまま、あれこれと考えていました。
きょうのお客様は憂うつです。大森の今井田さん御夫婦に、今年七つの良夫さん。夜学の先生の今井田さんは、四十ちかいのに、好男子みたいに色が白くて、いやらしい。奥さんは、小さくて、おどおどして、そして下品です。いまの世の中で、こんな階級、プチ・ブルの人たちが、一ばん悪いのではないかしら。
※プチ・ブル 「プチブルジョア」の略。

そう思いながらも「私」は、そんな気持ちを抑えて、愛想よく振る舞っています。けれども奥さんの「私」の料理に対する、しつこい無知なお世辞にはうんざりして、「窮余の一策なんですよ。」と事実を言ったつもりが、「うまいことをおっしゃる。」と笑い興じるのです。
今井田さんは、お母さんを連れて出掛けてしまいます。今井田御夫婦の厚かましさが、厭で厭で、ぶんなぐりたい気持ちがします。門のところまでお送りして、ひとりぼんやり夕闇の路を眺めていたら、泣いてみたくなってしまいます。
お座敷を掃いて、お風呂を沸かしながら『濹東綺譚』(永井荷風作)を読み返します。この作者の中でも、これが一ばん枯れていて、「私」は好きです。お風呂に浸っていると、肉体が、自分の気持と関係なく、ひとりでに成長して行くのが、たまらなく困惑します。

お風呂からあがって、なんだか今夜は星が気にかかって、庭に出てみます。星が降るようでした。黙って星を仰いでいると、お父さんのことをはっきりと思い出します。あれから一年、二年経って、「私」はいけない娘になってしまいました。ひとりきりの秘密を、たくさん持つようになりました。
お母さんが帰宅しました。お母さんの入浴後、「私」と二人でお茶を飲みながら会話を楽しみます。こうして夜に二人きりで夜を過ごすのも、ずいぶん久しぶりだったような気がします。お母さんが休んだあと、「私」はお風呂場で洗濯をします。十二時近くになっています。
窓からお月様が見えます。洗いながら、お月様に、そっと笑いかけてみます。お月様は、知らぬ顔をしていました。ふと、この同じ瞬間、どこかの可哀想な寂しい娘が、このお月様に、そっと笑いかけました。望遠鏡で見とどけたかのように、色彩も鮮明にくっきり思い浮かんだのです。

「私」たちの苦しみを、誰も知らないのだもの。大人になりきるまでの、この長い厭な期間を、どうして暮していったらいいのでしょう。世の中のひとは、「もう少しのがまんだ、あの山の山頂まで行けば、しめたものだ。」と、ただ、そのことばかり教えています。きっと、誰かが間違っています。わるいのは、あなたです。
明日もまた、同じ日が来るのだろう。幸福は一生、来ないのだ。それは、わかっている。けれども、きっと来る、あすは来る、と信じて寝るのがいいのでしょう。わざと、どさんと大きい音たてて蒲団にたおれます。
幸福は一夜おくれて来る。ぼんやり、そんな言葉を思い出す。幸福を待って待って、とうとう堪え切れずに家を飛び出してしまって、そのあくる日に、素晴らしい幸福の知らせが、捨てた家を訪れたが、もうおそかった。幸福は一夜おくれて来る。幸福は、――
おやすみなさい。私は、王子さまのいないシンデレラ姫。あたし、東京の、どこにいるか、ごぞんじですか?もう、ふたたびお目にかかりません。
青空文庫 『女生徒』 太宰治
https://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/275_13903.html
『女生徒』【創作の背景】

『女生徒』は、洋裁学校に通う、太宰作品の愛読者・有明淑(当時20歳)の日記を元に書かれています。太宰の妻・津島美知子は当時のことを次のように振り返っています。
練馬に住み洋裁学校に通っていたS子さん(大正八年生まれ)は昭和十三年四月三十日から日記を伊東屋の大判ノートブックに書きはじめ、八月八日、余白が無くなったときこれを太宰治宛郵送した。
(「女生徒のこと」『回想の太宰治』 津島美知子)
けれども8月に郵送した日記は、転居等の事情もあり、実際に太宰の手元に届いたのは翌年の2月でした。津島美知子は執筆当時の様子を次のように回想しています。
彼はこの日記を思いがけず得たことを天祐と感じ、早速この日記をもとにして小説を書き始めた。太宰は一読のもとに「可憐で、魅力的で、高貴でもある」(川端康成氏の『女生徒』評から)魂をさっとつかみとって八十枚の中篇小説に仕立て、(中略)「文学界」の十四年四月号に発表した。
(「女生徒のこと」『回想の太宰治』 津島美知子)
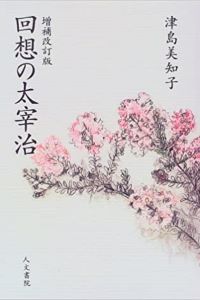
『女生徒』【解説と個人的な解釈】
本作品では文字通り、「女生徒」の、朝起きてから夜眠りにつくまでの一日が語られています。その間、思春期にありがちな女性の内面の揺らぎなど、様々な思考が展開されていきます。
主人公の「私」は、朝起きて鏡を見るたびに、眼鏡をかけている自分に劣等感を感じます。美しい目に憧れを抱いているのです。また文学少女の一面を持っている「私」は、あらゆる本から知識を得ているものの、そんな自分に疑問を抱いています。
さらには大人(特に成熟した女性)に対して、嫌悪感を抱いています。ずっと少女のままでいたいと願っているのです。母親との関係性にも悩み、母親にとって良い娘でありたいと思う一方で、反抗心も持つといった矛盾する自分の感情に戸惑っています。
「私」の心の中には、二年前に亡くなった父親の存在が、今も色濃く残っています。折にふれては思い出し、感傷的になります。そして、この世界のどこかに、自分と同じように思春期の悩みに苦しみ、月に笑いかけている女性がいることを思い浮かべます。言わば、救いを求めているのでしょう。
その一方で、「幸福は一夜おくれて来る」と、そんな言葉を思い出すような現実的な一面を持っています。そこには大人になっていく過程で誰もが通る「虚無感」や「絶望感」、つまり「やりきれない思い」が表れています。
物語は、「おやすみなさい。私は、王子さまのいないシンデレラ姫。あたし、東京の、どこにいるか、ごぞんじですか?もう、ふたたびお目にかかりません。」と「女生徒」の語りで結ばれます。
ここからは個人的な解釈になりますが、この結末の語りがどうも「女生徒」の強がりのように思えてなりません。本音では、苦しみを受け入れてくれる王子さまを待ちわびているよう気がするのです。けれども「女生徒」は知っています。幸福というものは訪れを願っているうちが華だということを。
あとがき【『女生徒』の感想を交えて】
.jpg)
わたし自身初めて『女生徒』という作品を手に取ったのも、ちょうど思春期真っ只中の頃だったように記憶しています。そして周りの同級生を見渡しては、(彼女達も同じ悩みを抱えているのかな?)と、想像を巡らしたものでした。
当然ながら当時は、元の日記の存在も知らず、「太宰って天才なんだな」と、感心したものです。それから時を経て、日記の存在を知ってから再読したのですが、だからと言って作品が色褪せたとは思いませんでした。
何故なら作中の個人的に好きな部分のほとんどが、太宰自身の筆によるものだったからです。ともかくとして『女生徒』という作品は、現在進行形で物語の主人公と同じような時期を過ごしている人のみならず、各年代の大人をも、忘れかけていた思春期へと誘ってくれます。
ちなみに太宰は、有明淑が三カ月余りかけて綴った日記を、起床から就寝までの一日の出来事に凝縮して作品に仕上げています。ですから主人公が、「人のものを盗んで来て自分のものにちゃんと作り直す才能は、そのずるさは、これは私の唯一の特技」と語る場面、―――それは太宰自身が、自らに放った皮肉のようにも聞こえます。
太宰治【他の作品】
太宰治『家庭の幸福』【家庭というエゴイズムへの反逆!】
太宰治『善蔵を思う』そしてわたしは、亡き友人を思う。
太宰治『黄金風景』読後、わたしの脳裏に浮かんだこと!
太宰治『燈籠』に見る【ささやかな希望の燈火と大きな暗い現実】
太宰治『富嶽百景』【富士という御山になぜ人は魅せられるのか】
太宰治・新釈諸国噺『貧の意地』あらすじと解説【心の貧困!】
太宰治・新釈諸国噺『破産』あらすじと解説【倹約ストレス?】
太宰治『清貧譚』あらすじと解説【私欲を捨ててまで守るもの?】
太宰治『ヴィヨンの妻』あらすじと解説【生きてさえいればいい!】
太宰治『葉桜と魔笛』あらすじと解説【神さまはきっといる!】
太宰治『待つ』あらすじと解説【あなたはいつか私を見かける!】
太宰治『水仙』あらすじと解説【21世紀にも天才は存在する!】
太宰治『メリイクリスマス』あらすじと解説【人間は逞しい!】
太宰治『雪の夜の話』あらすじと解説【随筆『一つの約束』!】
太宰治『薄明』あらすじと解説【絶望の淵に見る希望の光!!】
太宰治『たずねびと』あらすじと解説【他人からの善意の救済!】
太宰治『桜桃』あらすじと解説【子供より親が大事と思いたい!】
太宰治『斜陽』あらすじと解説【恋と革命のために生れて来た!】
太宰治『畜犬談』あらすじと解説【芸術家は弱い者の味方!!】
太宰治『満願』あらすじと解説【原始二元論と愛という単一神!】
太宰治『トカトントン』あらすじと解説【マタイ福音書の意味!】
太宰治『走れメロス』あらすじと解説【信頼されることの重み!】
太宰治『恥』あらすじと解説【小説家なんて人の屑だわ!】




コメント