はじめに【後悔先に立たず】
「後悔先に立たず」ということわざがあります。
今から思えば、“ あの時こうすればよかった。ああすればよかった ” と、わたしたちは過去を悔やみ続けながら生きていると言えるでしょう。
だけども過去というものは、思い出という形でしか、わたしたちは残せません。良い思い出ならまだしも、後悔などの辛い思い出ばかりを背負い続けていたら、やがてはくたびれ果て、前に進めなくなります。
人生を旅とするなら、背負う荷物は軽いほうがいいに決まっています。ですから時には立ち止まり、その荷物を軽くする必要があります。―――とは言うものの、簡単ではありません。結果、背負い続けるという選択をしがちです。
夏目漱石『こころ』の「先生」のように・・・。
人はなぜ悩むのか?【脳内の断捨離のすすめ!】
夏目漱石『こころ』あらすじと解説【真の贖罪とは何なのか?】
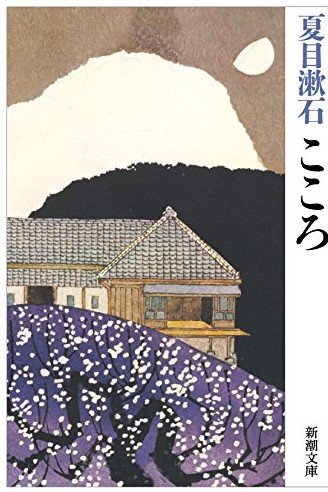
夏目漱石(なつめそうせき)とは?
夏目漱石(本名は夏目金之助)は日本の小説家、評論家、英文学者、俳人であり、明治末期から大正初期にかけて活躍した近代日本文学の頂点に立つ作家の一人です。(1867~1916)
夏目漱石は慶応3(1867)年、江戸牛込馬場下(現在の新宿区喜久井町)に生まれます。帝国大学英文科(現在の東京大学)卒業後、松山中学、五高(熊本)等で英語教師となります。その後、英国に留学しますが、留学中は極度の神経症に悩まされたといわれています。
帰国後は、第一高等学校と東京帝国大学の講師になります。明治38(1905)年、『吾輩は猫である』を発表し、それが大評判となり、翌年には『坊っちゃん』『草枕』など次々と話題作を発表し、人気作家としての地位を固めていきます。
明治40(1907)年、東大を辞して、新聞社に入社し、創作に専念します。本格的な職業作家としての道を歩み始めてからは、『三四郎』『それから』『行人』『こころ』等、日本文学史に輝く数々の傑作を著します。しかし、最後の大作『明暗』執筆中の大正5(1916)年12月9日、胃潰瘍が悪化し永眠してしまいます。(享年・50歳)

夏目漱石『夢十夜』【夢は本当に深層心理と関係があるのか?】
夏目漱石『現代日本の開化』要約と解説【幸福度は変わらない!】
夏目漱石『私の個人主義』要約と解説【他者の自由を尊重する!】
小説『こころ』について
『こころ(旧仮名:こゝろ)』は、夏目漱石の長編小説であり、漱石代表作の一つです。
『こころ』は、大正3(1914)年4月20日から8月11日まで、『東京朝日新聞』で『心 先生の遺書』として連載されました。
※ 『大阪朝日新聞』は休載回数が多かった為、大正3(1914)年4月20日から8月17日まで連載。
同年9月には、岩波書店より自費出版という形式で刊行されるのですが、当初の構想は、いくつかの短編を書いて、その総題を『心』とする予定でした。
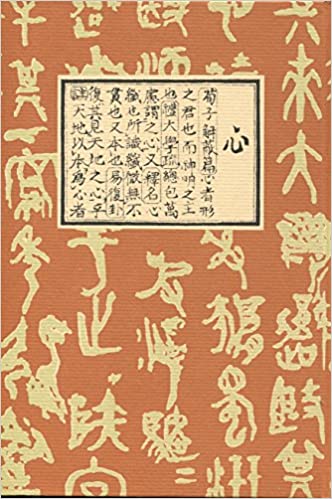
「(前略)今度は短編をいくつ書いて見たいと思ひます、その一つ一つには違つた名をつけて行く積ですが予告の必要上全体の題が御入用かとも存じます故それを『心』と致して置きます。(後略)」
(『心』予告『東京朝日新聞』大正三年四月十六日、『大阪朝日新聞』大正三年四月十七日掲載)
ところが、その短編の第一に当たる『先生の遺書』が長引きそうになったため、その一編だけを三部構成にして出版することにし、題名は『心』と元のままにしておいたと、単行本の序文には記されています。
『こころ』執筆の時代背景
日本の近代化を考える上で大きな転機となった明治という時代は、明治天皇の崩御(1912年7月30日)と共に終わりを告げます。そして大葬礼の日(9月13日)には乃木大将が殉死をします。この一件は当時の人々に大きな衝撃を与えました。
文学界においても乃木大将の殉死に対する反応は二分します。若い作家たちが批判する中、漱石は『こころ』を書いて「明治の精神」を訴え、批判を抑えようとしました。
乃木希典(のぎまれすけ)の殉死について

乃木希典は長州藩士として生まれ、戊辰戦争では東北を転戦します。明治維新後の西南戦争では歩兵一四連隊長として出陣しますが、植木の戦いで西郷軍に軍旗を奪われるという失態を犯します。このとき自決を決意しますが思い留まります。
その後、ドイツ留学を経て台湾総督を務めます。日露戦争では第三軍司令官となり、旅順を攻略します。同年大将に昇進し、伯爵を授けられます。けれども多数の将兵を戦死させた自責の念から、明治天皇に対し「自刃して罪を償いたい」と奏上します。
このとき明治天皇は「どうしても死ぬというのであれば朕が世を去った後にせよ」という趣旨のことを述べたとされています。乃木大将が自刃したのは大葬礼の日(9月13日)の午後八時頃です。それは明治天皇の棺を収めた車が皇居を出て、青山の葬儀場に向かう折、号砲が鳴らされた時間でした。
乃木希典の辞世の歌
うつし世を
神さりましし 大君の
みあとしたひて 我はゆくなり
妻・静子の辞世の歌
出でまして
かへります日の なしと聞く
けふの御幸に 逢ふぞ悲しき
『こころ』あらすじ(ネタバレ注意!)

上 先生と私
明治時代も末期の頃です。東京の大学に通う主人公の「私」は、夏休みを利用して、鎌倉の由比ヶ浜に海水浴に来ていました。そこで「私」は、一人の年配の男性と出会い、交流をするようになっていきます。
その男性のことを「私」は、―――「先生」と呼んでいました。
「私」はどういう訳か「先生」に惹かれていきます。そして東京に帰ったあとも「先生」の自宅を訪れる了解を得たのでした。
だけども最初に訪ねた日、「先生」は留守でした。二度目に訪ねた日も「先生」は外出していたのですが、奥さんが「毎月この日は、雑司ヶ谷にある友達の墓に墓参りに行く習慣になっているのです。」と教えてくれました。

そこで「私」は、その場所に行ってみることにします。「先生」を見つけた「私」が声をかけると、「先生」はどこか動揺している様子でした。墓地で「私」は、墓の形だの戒名についてあれこれと話します。
そんな「私」に対し「先生」は―――「貴方は死という事実をまだ真面目に考えたことがありませんね。」と、言いました。
「私」は回数を重ねて「先生」の自宅を訪問するようになります。「先生」は美しい奥さんと、そして一人の下女と一緒に暮らしていました。「先生」は大学出身にも関わらず、何もしていない様子です。

とにかく「私」にとって「先生」という人物は謎多き人物でした。「先生」は何度も訪ねて行く「私」を不思議がります。そして「自分は淋しい人間だ。」と繰り返し言い、「貴方も淋しい人間じゃないですか?」と聞きました。「私」は、それを否定します。
「先生」の物言いはいつも抽象的でした。上野の桜見物に行ったときも「先生」は、「恋は罪悪ですよ。そして神聖なものですよ。」と、謎めいた言葉を口にします。「私」はそんな「先生」に益々傾倒していきます。
そうした中、「私」は「先生」の奥さんと二人っきりになる機会がありました。その折に「先生」のことを色々と訊ねてみます。すると奥さんは「あの人は人間が嫌いなのです。」と言い「自分も嫌われているかも知れない。」と、告げたのでした。

そんなある日、「私」は父親が前々から患っていた腎臓病の経過がよくないという手紙を受け取ります。そこで「私」は、冬休み前に帰省をすることにします。故郷に帰って見ると、思っていたより父親は元気そうでした。
「私」は、久しぶりに接した父親と「先生」を比べて見ます。世間から認められることがないという意味では同じような人物でしたが、肉親の父親以上に「先生」は尊敬すべき存在なのだと始めて認識するのでした。「私」は東京に帰りたくなります。
東京に戻った「私」は卒業論文に没頭します。その論文も一段落した春、「私」は「先生」を散歩に連れ出します。そのとき「先生」は父親の病状を聞いてから不意に「君の家には財産があるんですか。」と、聞いてきました。

そして、こんなことを口にします。「悪人も普段はみんな善人なんです。それが急に悪人に変るんだから恐ろしいのです。」そんな会話の中で「私」は「先生」に、過去を打ち明けるように迫ります。
そのとき「先生」は、「あなたは私の思想と、私の過去をごちゃごちゃに考えている。」と拒絶します。けれども「私」は「人生から教訓を得たいのです。」と食い下がります。その言葉に「先生」は、「時が来たら全て話しましょう。」と、言いました。
大学を卒業した「私」は「先生」から食事に招かれます。二、三日後には帰省する予定になっていた「私」は、「先生」と奥さんに「当分お目にかかれませんから。」と、暇乞いの言葉を告げたのでした。

中 両親と私
帰省すると、両親は「私」の卒業を大変喜んでくれました。父親の病状も前とあまり変わらない様子でした。そんなとき―――明治天皇崩御の知らせが飛び込んできます。
この知らせの後、父親の容態は、みるみるうちに悪くなっていきます。「私」は東京へ帰る日を先延ばしにしました。そんな「私」に母親は、父親を安心させるために良い就職先を見つけなさいと口うるさく言います。
そして「私」の口からたまに話題に上る、その「先生」とやらに就職の斡旋を頼んでごらんなさいと、ついに言い出します。「私」は両親の手前、仕方なく「先生」に手紙を送ります。けれども、いつまで待っても「先生」からの返信はありませんでした。

父親の容態は、いよいよ危なくなっていきます。実家には、遠く九州に暮らす兄や親類などが集まりました。そんなとき「先生」から分厚い手紙が届きます。「私」は席を外して、その手紙を読もうとします。
すると、結末のほうの、ある文字が「私」の眼に入ってきました。
―――「この手紙があなたの手に落ちる頃には、私はもうこの世にはいないでしょう。」
手紙は「先生」からの遺書でした。「私」は咄嗟に、東京行きの汽車に飛び乗ってしまいます。そして客席に座ると同時に、その手紙の最初から最後まで、残らず眼を通したのでした。

下 先生と遺書
「先生」からの手紙には、このようなことが綴られていました。
「先生」は相当な財産家の一人息子でした。しかし「先生」が二十歳になる前に、チフスで両親を亡くします。その後、東京の大学に通うことになっていた「先生」は、財産の管理を信頼していた叔父に任せます。
ところが叔父は、その財産を使い込んでいたのです。「先生」は人間不信に陥ります。けれども法的に争うということまではせずに、残された遺産を整理し、郷里の新潟と決別しようと心に決めたのでした。
東京に出た「先生」は、ある母子家庭の家に下宿して大学に通います。そこには軍人の未亡人である気丈な「奥さん」と、その美しい一人娘の「お嬢さん」が暮らしていました。「先生」はこの「お嬢さん」に一目で惹かれます。

「先生」には「K」という同郷出身の友人がいました。
「K」は、浄土真宗のお寺の次男でしたが、医者の家に養子に出されます。そして養家から学資の援助を受けつつ、東京で医学を学ぶことを期待されていたのでした。
しかし「K」は本来、宗教や哲学のほうに関心が深く、東京で、実際には医学の勉強をしていなかったのです。このことが養家に知られ、学資の援助を打ち切られてしまいます。また実家からも勘当同然となっていました。
そこで「K」は、夜学の教師をして学資を稼ごうとします。ところが無理が重なり健康を害し、ノイローゼ気味になっていたのです。このことを知った「先生」は、下宿先に「K」を招き入れます。それは自尊心の高い「K」に分からぬよう、援助をする為でした。

「K」は中学でも高等学校でも「先生」よりも成績が優秀でした。容貌も「K」のほうが女性に好かれるよう見えます。ですから「先生」は、何もしても「K」には及ばないといった自覚がありました。
―――そんな「K」が「お嬢さん」と急激に親しくなっていきます。
「先生」の心は穏やかではいられませんでした。
夏休みに入ると「先生」は「K」を千葉への旅行に誘います。この機会に「先生」は自分の心を「K」に打ち明けようとしたのです。けれども中々言い出す機会は掴めずにいました。
この旅で二人は難しい問題を論じ合うことがありました。「お嬢さん」のことで頭がいっぱいだった「先生」は曖昧な言葉を返します。そのとき「K」は「精神的に向上心がないものは馬鹿だ。」と「先生」に向けて言い放ったのでした。

旅行から帰ってからも「先生」の「K」に対するわだかまりは、強くなっていく一方です。ある日には、「K」と「お嬢さん」が外で一緒にいるところを「先生」は目撃してしまいました。
そんなとき「K」から―――「お嬢さん」への恋心を打ち明けられます。
「先生」はその刹那、恐怖心に駆られ身体が動かなくなりました。そして(何故自分の心も打ち明けなかったのだろう)と、酷く後悔をするのでした。
そこで「先生」は一計を案じます。自己の鍛錬と恋心の狭間で悩む「K」に向けて、「K」が旅行中に口にした、「精神的に向上心がないものは馬鹿だ。」という言葉を投げかけたのでした。
そして「K」に先駆けて、「奥さん」に「お嬢さんを下さい。」と申し込みます。「奥さん」は快く了承してくれました。「先生」は思いがけず簡単に事が運んだことで不安になります。残るは「K」にこのことを説明するだけでしたが、中々話せずにいました。

それから五、六日後、「先生」は「奥さん」から、結婚のことを「K」に話したと聞かされます。そのとき「K」は、「おめでとうございます。」と言ったまま席を立ったと知らされました。
「先生」がこの事実を知らされた晩のことです。
―――「K」は、ナイフで頸動脈を切って自殺してしまいました。
「先生」は(もう取り返しが付かない)と思い、がたがたと震えだします。見ると机の上に手紙が置いてありました。「先生」は夢中で封を切り、それを読みます。ところが「先生」に対する恨みの言葉などは一言も綴られていません。「先生」はこのとき(助かった)と思います。
その後、家族は引っ越しをし、「先生」と「お嬢さん」は結婚をしました。その「お嬢さん」とは「先生」の奥さんのことです。そして「先生」が毎月訪れる雑司ヶ谷の墓とは、この「K」のお墓だったのです。

「先生」はそれから一人で “ 罪 ” を抱えながら生きてきました。そして “ 死 ” について真剣に考え続けてきたのです。すると夏に明治天皇が崩御になり、その一か月後に乃木大将が殉死をします。この二、三日後、「先生」は自殺を決心したのでした。
それからの「先生」は残りの時間を「私」宛の長い手紙に割きます。
手紙の最後にはこう綴られていました。
「私が死んだ後でも、妻が生きている以上は、あなた限りに打ち明けられた私の秘密として、すべてを腹の中にしまっておいて下さい。」
青空文庫 『こころ』 夏目漱石
https://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/773_14560.html
『こころ』【解説と個人的解釈】
「K」の死について
「K」は、己に対しストイックな人間でした。それは生まれた環境、そして宗教観や哲学からくるものです。「道のためには全てを犠牲にすべき」というのが「K」の信条でした。ところが “ 道ならぬ恋 ” をしてしまいます。
「K」は、自己矛盾なのを知りつつも、すがるよう「先生」に心を打ち明けます。それは養家、そして実家から縁を切られ、孤独だった「K」にとって、「先生」だけが信じられる存在だったからです。

尊かった過去の自分と、卑しい今の自分との狭間で苦悩する「K」に、「先生」の裏切りは残酷なものでした。結果、衝動的に自殺をしてしまったと考えるのが自然でしょう。
なぜなら、凄惨な死に方をすることで、(愛する人に衝撃を与えてしまうかもしれない)といった思慮に欠けているからです。残された遺書も、「自分は薄志弱行でとうてい行先の望みがないから、自殺する」と、ごく簡単なものです。
※ 薄志弱行(はくしじゃっこう) 意志が薄弱で物事を断行する力に欠けること。
遺書には「先生」に裏切られ、抜け駆けをされたとへの恨みつらみの文句は一言も記されていませんでした。しかし考えようによっては、凄惨な死に方をすることで、無言の抗議をしたとも思われます。
「先生」の死について

一方「先生」は、己の欲望のために「K」を欺くという、いわば叔父と同じ卑劣な行為をし、ついには取り返しのつかない事態を招いてしまいます。この過ちが生涯にわたって「先生」を苦しめます。
そして、卑劣な男だと思われたくないという「先生」の一種の自尊心が「奥さん」をも苦しめます。「奥さん」に対し “ 信仰に近い愛 ” をもっていた「先生」からすれば、それは耐え難いことだったのかもしれません。
すべては、「先生」の「K」に対する劣等感や嫉妬心から生まれた情念が招いた悲劇です。愛する人が傍にいるにも関わらず「自分は淋しい人間だ。」という「先生」もまた「K」と同じで心の中は孤独でした。
物語の表面上は、“ 裏切りの連鎖と一人の女性をめぐる愛憎劇 ” がもたらした二人の死ですが、忘れてならないのは、「自死への引き金」です。「K」はそれを失恋とし、「先生」は乃木大将の殉職にしました。もしかしたら二人は “ 死への理由付け ” を探していたのかもしれません。
あとがき【『こころ』の感想を交えて】

『こころ』はあくまで小説です。
ところがなぜでしょうか、あたかも読者自身の身の周りに起こった事柄のように伝わる不思議な感覚があります。
それは誰もが少なからず “ 罪 ” を犯しているからです。わたし自身、何人もの人間を傷つけてきたという自覚があります。その結果、知らないだけで、誰かを不幸に陥れているかもしれません。つまりは、贖罪の心を抱えながら生きているのです。
※ 贖罪(しょくざい) キリスト教で用いられる宗教用語。自分の犯した罪や過失を償うこと。罪滅ぼし。
では「先生」は、どのような形で贖罪をすれば良かったのでしょうか。「先生」の死は、次に「奥さん」を苦しめることになるでしょう。残された人間は必ず、先に逝った人間の “ 死の理由 ” を考え、思い悩むものです。
「先生」の「奥さん」への “ 信仰に近い愛 ” は自己愛に他ならないでしょう。真の贖罪を考えるなら、この負の連鎖は断ち切るべきでした。要らぬプライドなどかなぐり捨てて、全てを「奥さん」に打ち明けるべきでした。
わたし自身も『こころ』を読むたびに、贖罪の心が芽生えます。だけども、いくら悔やんでみたところで過去は取り戻せません。ですから、未来の行動こそが贖罪になるのだと自分に言い聞かせているのです。




コメント