はじめに【「文字の起源」について】
PCやスマートフォンの登場で、わたしたちの生活は格段に便利になりました。けれどもその一方で、ペンを握る機会が極端に減り、文字を書かなければならない場面で、簡単な漢字さえも忘れてしまい、恥を掻いた……なんて経験をした人も多いかと思います。
文明の発展は同時に、人間の能力を退化させる場合もあるようです。
さて、人類の「文字の起源」と考えられているのは、紀元前3500年~3000年頃のメソポタミア文明、シュメール人による絵文字とされていて、遺跡からは粘土版が発掘されています。
この絵文字は「ウルク文字」と呼ばれ、この文字はやがて「くさび型文字」へと変化していきます。また紀元前3000年頃にはエジプトでヒエログリフ(聖刻文字)が誕生します。
中島敦の短編小説『文字禍』は、このメソポタミア地方、古代オリエント最初の統一国家、アッシリア(現在のイラク北部を占める地域)が舞台となっています。
中島敦『文字禍』あらすじと解説【「執着」は人間を崩壊へと!】

中島敦(なかじまあつし)とは?
昭和初期に活躍した小説家です。中島敦(1909-1942)は東京に生まれ、東京帝国大学国文科を卒業後、横浜高等女学校で教壇に立つかたわら執筆活動を始めます。
持病の喘息と闘いながらも執筆を続け、1934年、『虎狩』が雑誌の新人特集号の佳作に入ります。1941年、南洋庁国語教科書編集書記としてパラオに赴任中、中島代表作のひとつ『山月記』を収めた[古譚]を刊行しました。
その後、創作に専念しようとしましたが、喘息が悪化し、急逝してしまいます。(享年33歳)
『弟子』『李陵』等の代表作の多くは死後に発表され、その格調高い芸術性も死後に脚光を浴びることになります。

中島敦 南島譚01『幸福』を再読した感想!!
中島敦『寂しい島』を再読し、改めて感じた想い
中島敦『盈虚』あらすじと解説【権力への執着とその虚しさ!】
中島敦『名人伝』あらすじと解説【幻影を祭り上げる群衆心理!】
中島敦『山月記』あらすじと解説【臆病な自尊心と尊大な羞恥心!】
中島敦『弟子』あらすじと解説【認め合う美しき「師弟愛」!】
短編小説『文字禍』(もじか)について
『文字禍』は、『山月記』と共に、『古潭』の総題のもと『文學界』昭和17(1942)年2月号に掲載されます。その後『古潭』四篇(『山月記』『文字禍』『狐憑』『木乃伊』)として、第一創作集『光と風と夢』に収録されます。
『文字禍』あらすじ(ネタバレ注意!)

アシュル・バニ・アパル大王の治世第二十年目の頃、ニネヴェの宮廷に妙な噂が立ちました。それは、毎夜、誰もいない図書館の闇の中で、ひそひそと怪しい話し声がするというものです。
それを「文字の霊(というものが在るとして) 」の声と考えた大王は、ナブ・アヘ・エリバ博士を呼び出して、この未知の霊について研究するように命じました。その日以来、博士は、図書館に通って、万巻の書の研鑽に耽るようになります。
※万巻(まんがん) 多くの巻物。多数の書物。
※研鑽(けんさん) 学問などを深く究めること。
当時メソポタミアで紙は無く、文字は瓦のような粘土の板に掘りつけられていました。博士はその重量のある古知識の中から、「文字の霊」について探しましたが、徒労に終わってしまいます。
そこで博士は書物を離れ、ただ一つの文字を前に、終日それと睨めっこをして過ごしました。そのうちおかしな事が起こります。見つめている文字が解体し、意味のない線の交錯としか見えなくなってきたのでした。
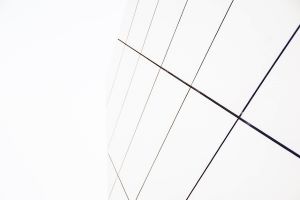
この不思議な事実を発見した博士は、「文字の霊」の存在を認めます。この発見を手始めに博士は、街中を歩き回って、最近文字を覚えた人を訪ね歩きました。博士は、「文字の害たる、人間の頭脳を犯し、精神を麻痺せしむる。」と備忘録に記します。
文字を覚える以前に比べて、職人は腕が鈍り、戦士は臆病になり、猟師は獅子を射損なうことが多くなったと言うのです。博士は、文字の無かった昔は、歓びも知恵も全部直接人間の中に入ってきたとし、「近頃の人々は物覚えが悪くなった。」これらは「文字の精の悪戯」だと結論づけます。
博士は、ある書物狂の老人を知っています。その老人は博士よりも博学ですが、その日の天気や隣人の不幸に、まるで気が付きませんでした。けれどもこの老人は、羨ましいほど幸福そうに見えます。博士はこのことも「文字の霊の魔力」と見做しました。

また青年らの浅薄な合理主義を一種の病と考え、この病を流行らせたのも「文字の霊」と考えます。ある日若い歴史家が博士に訊ねました。「歴史とは昔在った事柄、それとも文字のことを言うのであろうか?」
※浅薄(せんぱく) 知識や考えが、浅く薄っぺらなこと。浅はかなこと。
博士は答えます。「昔在った事柄で、かつ文字によって記されたものである。」更に歴史家は、「書き漏らしは?」と訊ねました。すると博士は、「書かれなかった事は、無かった事じゃ。」と答えたのでした。
だいぶ前から博士も「文字の霊」による恐ろしい病にかかっていました。文字の分解はおろか、家や人間などあらゆるものが分解されて見えるようになる「奇体な分析病」に罹っていたのです。

博士は、これ以上研究を続けることは生命の危険だと思いました。そこで博士は大王に、「文字への盲目的崇拝を改めるよう」といった研究報告を献じます。この報告書は大王の機嫌を損ねました。博士は謹慎を命じられます。
博士はこれを「文字の霊の復讐」と悟りました。そして謹慎中、ニネヴェ・アルベラの地方を襲った大地震で、夥しい書籍―――数百枚の重い粘土板の下敷きになり、博士は圧死してしまったのでした。
青空文庫 『文字禍』 中島敦
https://www.aozora.gr.jp/cards/000119/files/622_14497.html
『文字禍』【解説と個人的な解釈】

物語に登場する「文字の霊」というものについて現代人なら首をかしげるのも当然でしょう。けれども物語は冒頭でも話したように、古代オリエント最初の統一国家、アッシリアです。日本で古くから「怨霊」が信じられていたように、アッシリアでも「霊」は存在するものとして認識されていました。
この前提を踏まえ『文字禍』を解説すると、古代人は実態の分からない現象全てを「霊」もしくは「精霊」として考えていました。ですからアシュル・バニ・アパル大王がナブ・アヘ・エリバ博士に「文字の霊」の研究を命じるのも頷けます。
やがて博士はその研究の過程で、「奇体な分析病」に罹ってしまいます。博士はそれを「文字の霊」の仕業だと結論づけます。一方で、書物狂の老人を例に出して、「幸福そうに見える」と語ります。博士にとっては「毒」の「文字の霊」も、老人にとっては「媚薬」だったのです。
調査結果を報告した博士は大王の機嫌を損ね、謹慎を命じられます。奇しくもその謹慎中に粘土板が降りかかって博士は圧死します。このことを「文字の霊の復讐」としていますが、実際は「自然災害による死」です。
そもそも博士は、自分自身が「文字」に執着し、挙句には崩壊していくことだけで「文字の霊」の存在を認めています。いわゆる自分の「先入観」で研究結果を纏めているのです。この「先入観」に政治的な意見を加えて報告するのですから大王の機嫌を損ねるのも当然です。
悲しいかな、人間というものはどんなことでも、自分に都合の良いように解釈してしまうものです。博士の場合は「先入観」と言うよりも「思い込み」と言ったほうが正しいでしょうか。ときに「思い込み」や「執着」は、人間を崩壊へと導いてしまうものなのです。
あとがき【『文字禍』の感想を交えて】

冒頭でも話したように、わたしたちの暮らしはPCやスマートフォンの登場で格段便利になりました。あらゆる情報も、『文字禍』の博士のように重量のある書物を探さなくても、指先一つで即座に手に入れられるようになりました。
その一方で、偽情報を含めた情報の波に日々飲み込まれています。ときにはその偽情報で溺れかけることも……。まさに現代社会は「情報の文字禍」とも言えるでしょう。
中島敦は儒学者の家に生まれ、幼き頃より漢学を叩きこまれました。小説家を目指す過程で、アッシリアや古代エジプトの歴史を勉強したといいます。けれども同じ頃、持病の喘息の発作が酷くなっていきました。
思うのですが中島は、博士の姿に自分を重ねていたのかも知れません。文字に取り憑かれている自分の姿を。あるいは幸福そうな書物狂の老人の方でしょうか。そうあって欲しいと願います。ともかくとして、現代人は「情報の文字禍」にだけは気を付けなければなりません。勿論わたし自身も。




コメント