はじめに【『餅』への執念――後日談!】
介護老人の飽くなき『餅』への執念!【お餅受難騒動始末記】 にて、父親の餅好きについて書かせて頂きました。そのとき述べたように、餅は一口で飲み込める程度に小さく切り、それに加えて、食べるときは必ず付き添いをするといった、わたしなりに出来る限りのことをして、無事に正月を越せたと思っていました。
思っていました。―――どうして過去形かと言うと、先日、オーブントースターのなかに、焼いたままの形で置き忘れた餅が入っていたのを見つけてしまったからです。父親の寝室を探索したところ案の定、○○の切り餅と黄な粉と砂糖が、タンスのなかに隠されていました。
「これはなんだ?」と、問い質しても知らないの一点張りです。それどころか最近は痴呆症を逆手に取り、自分にとって都合の悪いことになると(もしかしたら、ボケているフリをしてる?)と、疑ってしまうような言動が顕著に見て取れます。
つまり、あれほど “ 誤嚥 ” の予防を考えた、わたしなりの努力も虚しい結果に終わってしまったのです。挙句の果てに、わたしがうるさく言うと、「好きなものを好きなだけ食わせて死なせろ!」なんて、逆切れされる始末です。
そんなとき、わたしの脳裏に、(それなら毎日、三食餅だけを食べさせて、「もう餅なんか一生見たくない!」と言わせてやろうか。)といった、邪悪な思考が現れたりします。
芥川龍之介の短編小説『芋粥』のように・・・。
芥川龍之介『芋粥』から学ぶ【人間的欲望の本質!!】

芥川龍之介とは?
大正・昭和初期にかけて、多くの作品を残した小説家です。芥川龍之介(1892~1927)
芥川龍之介は、明治25(1892)年3月1日、東京市京橋区(現・東京都中央区)で牧場と牛乳業を営む新原敏三の長男として生まれます。
しかし生後間もなく、母・ふくの精神の病のために、母の実家芥川家で育てられます。(後に養子となる)学業成績は優秀で、第一高等学校文科乙類を経て、東京帝国大学英文科に進みます。
東京帝大英文科在学中から創作を始め、短編小説『鼻』が夏目漱石から絶賛されます。今昔物語などから材を取った王朝もの『羅生門』『芋粥』『藪の中』、中国の説話によった童話『杜子春』などを次々と発表し、大正文壇の寵児となっていきます。

夏目漱石
夏目漱石『夢十夜』【夢は本当に深層心理と関係があるのか?】
夏目漱石『こころ』あらすじと解説【真の贖罪とは何なのか?】
夏目漱石『現代日本の開化』要約と解説【幸福度は変わらない!】
夏目漱石『私の個人主義』要約と解説【他者の自由を尊重する!】
本格的な作家活動に入るのは、大正7(1918)年に大阪毎日新聞の社員になってからで、この頃に塚本文子と結婚し新居を構えます。その後、大正10(1921)年に仕事で中国の北京を訪れた頃から病気がちになっていきます。
また、神経も病み、睡眠薬を服用するようになっていきます。昭和2(1927)年7月24日未明、遺書といくつかの作品を残し、芥川龍之介は大量の睡眠薬を飲んで自殺をしてしまいます。(享年・35歳)

芥川龍之介
物語『芋粥』について
『芋粥』とは、大正5年(1916年)9月の『新小説』に発表された芥川龍之介の短編小説です。
『今昔物語集』の巻26第17話「利仁の将軍若き時京より敦賀に五位を将て行きたる語」を下敷きとしていて、『鼻』と並んで古典翻案ものの一つと位置づけられています。
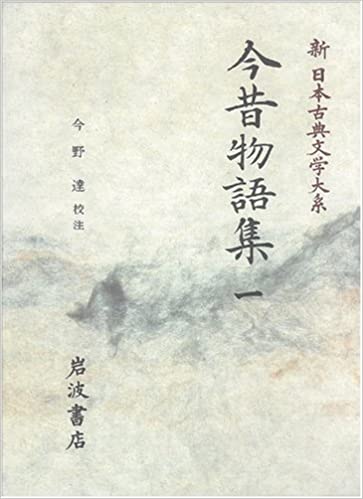
『芋粥』あらすじ(ネタバレ注意!)
平安朝という遠い昔、摂政藤原基経に仕える某という、身分は五位の男がいました。
五位は背が低く、風貌はと言えば、赤鼻で、目尻が下がっていました。つまりは風采の上がらない男で、年はすでに四十を越しています。
そのような男でしたから、下の身分の者たちにも相手にされず、まるで空気かのように扱われていました。ですから、上役の者たちも五位を相手にしないのは当然でしょう。悪意に満ちた態度で、なにを伝えるにしても手真似だけで用を足すのでした。

けれども五位は、そんなことで腹を立てたこともありません。要するに、そういうことを言い咎める勇気が無いほど五位は臆病だったのです。ところが、同僚たちもときには性質の悪い悪戯をするときがあります。
そうした折には――「いけぬのう、お身たちは。」と、呟くのでした。
そんな、五位でしたが、何の希望も持っていないかと言うと、そうではありません。芋粥というものに異常な執着を持っていました。芋粥とは山の芋を中に切込んで、それを甘葛(あまの汁で煮た、粥の事を言います。
それは当時、身分の高い人の食膳にしか出されない、とても貴重な料理で、五位の侍の口に入るのは年に一度だけ、それもほんのわずかで、喉を潤す程度の少量でした。ですから「いつの日か、芋粥を飽きるほど飲んでみたい。」というのが、唯一の欲望になっていたのです。
ある年の正月のことです。摂政関白家が饗宴を催され、五位も外の侍たちに混じって酒宴の残りものを頂くといった機会に恵まれます。その残りもの中に、例の芋粥もありました。五位は毎年、この芋粥を楽しみにしているのです。
ところがこの年は、例年よりも参加人数が多く、五位の飲める量はほんの少しでした。だからなのかも知れませんが、いつもよりも美味しく感じたのです。五位は空の椀を眺めながら、「何時になったら、これに飽きる事かのう。」と、思わず呟いてしまいます。
この呟きに反応した誰かが「大夫殿は、芋粥に飽かれた事がないそうな。」と、嘲笑いました。声の主は、同じ基経に仕える藤原利仁です。利仁は身分も高く、逞しい体格をそなえていて、見るからに武人そのものといった豪快な男です。

利仁は、「お望みなら、利仁がお飽かせ申そう。」と、言います。五位は周りの視線が自分に集まっているのを感じて、返答に困ってしまいます。返答次第でまた周りから嘲弄を受けなければなりません。結局は、どのように答えようと馬鹿にされるような気もします。
窮した五位は、「忝のうござる。」と答えてしまいます。思った通りで、一斉に失笑の声があがりました。利仁はその返答に機嫌よく大笑いし、「では、そのうちに、御誘い申そう。」と、言いました。五位もまた「忝のうござる。」と、周りに笑われながらも答えるのでした。
五位にとっては、もはやこの嘲弄も苦にはなりません。目の前に置かれた酒や肴にも手をつけません。それは、芋粥の二文字が頭の中を支配して、夢心地になっているからです。
それから四、五日たった日のことです。利仁と五位は馬に乗って出かけることになりました。五位は利仁に「どこに向かうのか。」と、訊ねてみるのですが、利仁は「もう少し先じゃ。」と、言うばかりで、行き先を明かしてはくれません。

そうこうしているうちに、近江の湖(琵琶湖)が見えてきました。そこでやっと利仁は行き先を明かします。「実はな、敦賀(現在の福井県)まで、お連れ申そうと思うたのじゃ。」五位は狼狽してしまいます。この通りは盗賊が出没することで有名だったからです。
そんな五位の狼狽にも利仁は嘲笑うだけで馬を先に進めます。不安で仕方のない五位でしたが、利仁に従って着いて行くより方法はありませんでした。道すがら一行は一匹の野狐に出くわします。
利仁はその狐を捕まえて、「敦賀の館に行って、明日の巳の時頃(現在の午前10時ごろ)、高島まで迎えにくるよう伝えろ。」と、言付けをし、狐を放しました。一行は翌日に予定通り、高島に着きました。すると、本当に二、三十人の従者が待っていたのです。

聞くところによると、狐は約束通り、敦賀の館にいた奥方に乗り移って言付けを伝えたと言うのです。こうして無事敦賀に着いた一行でしたが、五位の心には何だか妙な不安が押し寄せてきました。芋粥への待ち遠しさと同時に、その時間が早くきてはならないような心持もするのです。
この矛盾する二つの感情に、五位は戸惑います。そのせいか夜も眠れずにいたのです。外からは山芋についての命令を下す声が聞こえてきます。五位は益々、芋粥にありつきたくないという思いに駆られます。折角の今まで辛抱が無駄になってしまうような気がしたからです。
そして、ついにこの日がやってきました。庭には大量の山芋が運ばれ、大きな釜が五つ六つ備え付けられ、何十人もの女性が、まるで戦場を思わせるような騒ぎで調理に勤しんでいました。五位はこの光景を見て、自分が、その芋粥を食べる為に京都から、わざわざ、越前の敦賀まで旅をして来た事を考えます。

そのことを考えれば考えるほど、芋粥への食欲は失せていきます。そんな五位の目の前に溢れんばかりの芋粥がいくつもの膳に乗せて運ばれてきました。利仁の舅有仁は五位に言います。
「芋粥を飽きるくらい召し上がったことが無いそうで、どうぞ、遠慮なく召し上がって下され。」
五位は眼をつぶって、いやいやながらも芋粥を飲み干しました。利仁は意地悪く「父もこう言っているので、遠慮は無用じゃ。」と、催促します。五位は弱ってしまいます。正直に言えば、芋粥は一椀も吸いたくありませんでした。これ以上食べたら戻してしまいそうです。

それでも五位は、利仁や有仁の厚意を無駄にしないように、我慢をして椀に口をつけました。そして、「何とも、忝のうござつた。もう十分頂戴致しました。」と、言います。
五位は、ここに来ない前の自身を懐かしく、心の中でふり返ります。それは多くの侍たちに愚弄されている彼の姿でした。それと同時に、芋粥に飽きたいという欲望を、唯一大事に守っていた、幸福な彼の姿でした。
青空文庫 『芋粥』 芥川龍之介
https://www.aozora.gr.jp/cards/000879/files/55_14824.html
甘葛(あまづら)とは?
古代から用いられた日本の甘味料。中世後期に砂糖の輸入がはじまり,近世になってその国内生産が増大するとともに,位置をゆずって消滅した。アマズラと呼ぶ植物からとった汁を煮つめたもので,甘葛煎(あまずらせん),味煎(みせん)とも呼ばれた。
原料植物のアマズラについては諸説があり,ツタの1種とかアマチャとかいわれるが,ツタが正しいようである。《延喜式》には伊賀,遠江以下20ヵ国と大宰府から毎年貢納されたことが見え,宮中の大饗(たいきよう)などではこれでヤマノイモを煮た芋粥がしばしば供されている。
出典:株式会社平凡社/世界大百科事典 第2版
あとがき【『芋粥』の感想を交えて】

『芋粥』の原文で芥川はこんなことを言っています。
人間は、時として、充されるか充されないか、わからない欲望の為に、一生を捧げてしまふ。その愚を哂ふ者は、畢竟、人生に対する路傍の人に過ぎない。
“ 誤嚥 ” のリスクがありながらも、餅に執念を燃やす父親のことを、半ば心の底で笑っていたわたしも、言うなれば路傍の人だったと言えるのかも知れません。そこは反省すべきです。
人間として生まれてきた以上、欲望はわたしたちの身体、そして心へと、影のように付きまとってきます。どこで折り合いをつけるかは、その人しだいです。五位の場合は、芋粥への欲を望む(夢に見る)というところまでが、欲望の本質だったのでしょう。
さて、わたしの父親の、餅への欲望の話に戻りますが、いつだったか呆れ果てたわたしは、父親にこんなことを質問しました。
「餅を我慢して長生きするのと、我慢しないで早く死ぬのとどっちがいい?」
父親は大真面目な顔でこう答えました。
「なんにも我慢しないで、好きなことだけして、長生きがしたい。」
もはや父親の辞書に、二者択一という言葉はないようです。
芥川龍之介【他の作品】
芥川龍之介『蜘蛛の糸』あらすじと解説【お釈迦様の教えとは?】
芥川龍之介『杜子春』に学ぶ人生観【人間らしく正直に生きる!】
芥川龍之介『おぎん』あらすじと解説【信仰よりも肉親の情!】
芥川龍之介『羅生門』あらすじと解説【生か死か、善か悪か!】
芥川龍之介『捨児』あらすじと解説【血は繋がっていなくても!】
芥川龍之介『トロッコ』あらすじと解説【憧れ・喜びが恐怖へ!】
芥川龍之介『舞踏会』あらすじと解説【ヴイのような花火!!】
芥川龍之介『枯野抄』あらすじと解説【松尾芭蕉の臨終!!】
芥川龍之介『鼻』あらすじと解説【人間の矛盾する二つの感情!】
芥川龍之介『桃太郎』あらすじと解説【鬼が島は天然の楽土!】
芥川龍之介『蜜柑』あらすじと解説【純粋無垢な姉弟の思いやり!】
芥川龍之介『藪の中』あらすじと解説【真実は当人のみぞ知る!】
芥川龍之介『二人小町』あらすじと解説【死の恐怖と生への執着!】
芥川龍之介『おしの』あらすじと解説【宗教的価値観の相違!】




コメント